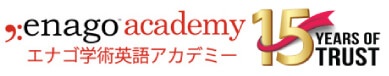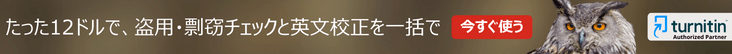林尭親氏へのインタビューー多様化する宗教観の研究を通して、多文化共生の在り方を考えたい

日本初の学術系クラウドファンディングサイト「academist」を運営するアカデミスト株式会社が実施する、若手研究者を対象とした研究費支援プログラム「academist Prize」。エナゴが協賛する同プログラム第4期の採択者である、京都大学大学院 教育学研究科 教育学環専攻 教育認知心理学講座 博士課程在籍中で、日本学術振興会特別研究員の林尭親氏に、書面インタビューでお話を伺いました。
1. 日本文化を対象として、多様な価値観が共生する現代の生き方を考える研究を行われています。いつごろ、どのようなきっかけで今の研究テーマに興味を持たれましたか?
日本文化を研究したいという気持ちは、大学の頃から考えていたことでした。大学時代はアメリカにいたので、いろんな文化に触れる中で自然と文化比較に興味がわき、せっかく研究するなら自分がよく知る文化を研究しようと思いました。
その中でも特に宗教に興味がわき、学部時代から専攻していた心理学分野での研究を始めました。最初は自分の興味に従って研究を進めていましたが、修士課程2年(M2)の頃ぐらいから研究費の申請書などを書いたり、スタートアップでインターンをしたりする中で、自分の研究の社会的意義について考えるようになりました。宗教間紛争は宗教的な価値観の違いに起因する争いですが、このような思想や価値観の違いを乗り越えることが社会における課題の一つであると考え、多様な価値観がある現代社会の生き方を考えたいと思うようになりました。
2. academist Prize 第4期でクラウドファンディングに挑戦中のプロジェクトについて教えてください
現在挑戦中のプロジェクトは、自分でも挑戦的なプロジェクトのつもりです。普段通り研究を進めていけばよいという感じではなく、自分が研究を進めていくことでどのように社会に還元できるかをテーマにしています。
例えば、僕の研究領域でもある文化心理学と呼ばれる分野では、「どのような概念で文化差がみられるか」に焦点が当てられその文化差を生み出す原因やメカニズムに焦点を当てる研究が重視されます。一方でグループダイナミクスと呼ばれる分野ではこのようなメカニズムや原因を理解したうえでどのような方法を用いればよりよい社会活動が実現するかを考えます。このプロジェクト(そして今年の僕の研究)はこの両方―つまり宗教観や文化差が生まれるメカニズムの基礎的な研究とその知見を社会に活かす応用的な研究―をしたいと考えており、その実現のために宗教に関する多くの方の視点や意見を取り入れながら活動していくということを大事にしています。
ですので、ご支援いただいている方に僕の方から一方向的に発信するというよりは、サポーターの皆さんにご自身の宗教の事や宗教に対する考えをたくさん教えてほしいと願っています。実際、プロジェクトの開始から多くのサポーターの方に宗教研究や宗教そのものについて教えてもらい、僕も日々勉強させてもらっているという感じです。
3. academist Prize 第4期にアプライした理由は何ですか?
academistを知ったきっかけは、今回同じacademist prize第4期に挑戦している櫃割さんと渡部さんでした。実は櫃割さんは僕のラボの先輩で、今までもいくつかの共同研究をさせてもらっているとってもお世話になっている研究者の一人です。また、渡部さんも同じ京大心理系の先輩で、修士の頃からいろんな場面でお世話になっています。
その上で第4期に応募した理由は、2の回答でも少し触れましたが、宗教の研究では本で読んだ知識はもちろん、個人的な体験や経験も重要であると感じているからです。これは他の心理学系の研究テーマにも当てはまる―例えば記憶の研究をするときには自分で何かを思い出してみて思考実験をする―ことだと思いますが、とりわけ宗教心理学ではどれだけ多種多様な宗教について体系的に理解しているかという知識の広さに加えて、自分の研究の軸となる宗教やその宗教が浸透する文化に精通するといったような知識の深さも必要であると考えています。
例えば、キリスト教といってもカトリック、プロテスタント、正教会などに分かれたり、プロテスタントのなかでもバプテスト、ルーテル、カルヴァンなど多くの教派が存在します。優れた研究をするにはMECE(Mutually Exclusive、 Collectively Exhaustive)な群・条件分けは必要不可欠ですが、教派や宗旨を包括的に理解し研究の主張が筋の通っているものにすることはとても重要です。
僕も正直理解し切れていない宗教の方が多いと思いますが、研究をする際にはその教派の方々や宗教に詳しい先生方にご指導をいただきながら逐次知識を蓄積し、明瞭な仮説を立てることを心がけています。また、そもそも神社に行ったときに感じるどこかすっきりする感覚やお寺に行ったときに自分とより向き合えることなど、実際にそれを体験してみないとそもそもの研究の疑問が浮かんできにくいと思います。
少し脱線しましたが、宗教の概観をつかむという意味でも、もっと深い宗教的な体験を知るという意味でも僕が独学のような形で知識を体得していくには限界があります。よりリアルで十分に意味のある研究をするためには、多くの方々が独自に経験されてきたことやその人のレンズでみてきた宗教を僕が学びたいという気持ちもあり、多くの方に研究を届ける1000 True Fansの目標を掲げる第4期に応募しました。
4. 宗教の概念という、一見、量では計れなさそうなものを「定量的に検討」する場合、具体的にどのような手法を取られるのですか?
心理学分野において感情や認知のようなものを定量的に測るには長らく質問紙(尺度・アンケート)が用いられており、僕が実施する多くの研究も質問紙を使用しています。
質問紙は認知や感情を定量的に測定できる方法ではありますが、一方で社会的望ましさ(自らの素直な意見ではなく社会にとって望ましい回答をしてしまう傾向)や自由な想起による回答ができない(質問紙の文章をみて「あーそういう考え方もあるのか」と思ったりする)という弱みがあります。そこで、潜在連合テスト(implicit association test)と呼ばれる無意識的・潜在的な感情や認知を測定する方法を用いたり、インタビューや自由記述のデータをテキストマイニングや機械学習などの手法を用いて定量的に扱うといった方法も同時に採用することが多いです。
宗教の概念についていえば、宗教へのコミットメント(どれだけその人が信仰する宗教のイベントや個人的活動に打ち込んでいるか)や宗教の中心性尺度(自分の人生において宗教が他の要素と比べてどれくらい大切か)などの質問紙があります。しかし、「宗教性」や「スピリチュアリティ」という宗教心理学で一般的に用いられる構成概念が何を意味するのかという議論は常に続いており、著名な研究者の一人は「あまりに多様で個人によってその定義が異なるため宗教性のようなビッグワードの定義は不可能である」という見解を述べています。僕も原則としてこの主張に賛成していて、宗教性やスピリチュアリティを定義することはこの分野における重要なイシューではないと思っています。むしろ実施する研究ごとに宗教性のある側面を切り取った定義(機能的定義)をし、それが社会における他の要素とどのように関連しているかを検討することがよいと思っています。
5. ほとんどの人が一神教以外の宗教を信仰していたり、自分を無宗教だとみなしたりする、日本人の宗教に対する概念は無限に広いのではないかと思いますが、実験前に仮説を立てたり、明確な結果を導き出すのは難しくありませんか?
これは、「まさしくその通り!」という感じです(笑)。特に仏教と神道の線引きは日本においてはほとんどできないような感じがあります。自分が実施した実験でも神道信仰者の多くは仏教(曹洞宗などの禅宗)の考えを肯定的にとらえますし、曹洞宗の多くは神道のアニミスティックな世界観を受容するので、両方合わせて日本人によくみられる宗教形態というのが体感としてしっくりきます。もちろん日蓮宗や浄土宗・浄土真宗と曹洞宗は性質的に異なるところも多くあると思うので仏教をひとくくりに考えることは難しそうですが…。
それから無宗教の定義も難しいポイントだと思います。無宗教という言葉は読んで字のごとく信仰する宗教が無いということですが、これもすべての宗教を知ったうえで信仰するものがなかったのか、自分がイメージするキリスト教や仏教は信仰していないという非宗教的な感じなのか、それとも積極的に宗教というものに嫌悪感があるような無宗教なのかの分類などもできます。日本では、キリスト教が主張するような全知全能で唯一の神というものを信じられないので無宗教という人が多いですが、パワースポットの存在や自分が知覚できない何かしら大きい力の存在を信じる人は多い印象です。
この様な日本人の曖昧で複雑な宗教性を鑑みると、やはり仮説を立てることはかなり難しいと思います。多くの場合欧米の先行研究において指摘されていたことが日本文化では見られないと仮定したり、その逆で日本の宗教ではもっと重要視されていることがあるというようなことを述べて、研究する宗教の宗旨から導かれるデータの予測をすることが多いです。ただこのような宗教の形は伝統的な宗教の影響力が小さくなってきた現在における新しい宗教の形と似ているところがあり、その点において日本はとてもよい研究対象であると思っています。
6. 特定の宗教団体に属していない限り、宗教について話す機会そのものが日本にはあまりないのかと思います。林さんが、他にも無数にあるだろう研究手法の中から特に「宗教観の考察」を選び、それを通じて「多文化共生の在り方」を考えたいと思われた背景・原体験をお聞かせいただけますか?
一番の原体験はイスラム教の友達との交流かなと思います。大学時代、サウジアラビアからきていたイスラム教徒のカップルの家に居候していたのですが、そこでかなり‘攻めた’質問をしたりしていました。当時の僕はあまり宗教に見識がなく、その分純粋な質問をよくしていました。例えば、「なんで神様がいると思うの?」「死んだらどうなる?」「キリスト教やユダヤ教のことはどう思う?」「イスラム過激派組織の考えや行動についてどう思う?」など、本当に多くの―ときに気分を害するような―疑問をたくさんぶつけてしまいましたが、その二人は、長くアメリカに住む比較的リベラルなサウジアラビア人でしたが、本当に広い器で彼らの考えや思いを伝えてくれました。
一緒に暮らしていると、もちろん宗教観のような一見身構えてしまうテーマだけではなく、(ラマダンなどの宗教的行事を含む)食事に対する考え方や人との付き合い方、仕事との向き合い方や人生の目標など彼らの文化について知るうちに仲良くなりました。時には喧嘩しながら議論をしたこともありますが、宗教観が違っていても相手に興味を持ちリスペクトをもってコミュニケーションをとれば思想を乗り越えた共生ができる、その片鱗を感じた大切な原体験として残っています。
7.<「曖昧」かつ「寛容」な宗教性を持つ日本文化に焦点を当てることは、増えつつある「宗教の個人化」を解明する絶好の研究対象>とされていますが、「宗教の個人化」は世界的な潮流なのでしょうか。世俗化の亢進は、むしろ宗教の側には、個人化を許容しない原理主義化を促すようにも思われるのですが(例:アメリカ福音派)、「宗教の個人化」に関して日本の特殊性があればお教えください
宗教の個人化や世俗化のトレンドについては様々な見解があり、個人的にも一様に個人化が進んでいるとは言えないと思っています。福音派だけではなく原理主義的な活動が盛んになったという事例も世界中でありますし、むしろ古くに予測された世俗化は思ったより進まなかったという印象もあります。一方でニューエイジムーブメントに代表されるように、キリスト教国においても仏教や禅、その他の東洋思想を取り入れる動きはいまだ見られます。
日本における宗教の個人化についての実証的な研究はあまり多くないと思いますが、日本人がある種非常に個人主義的に個々人が独自の宗教性を心の中で築くと同時に、祝祭時やイベント、またそれに付随するコミュニティを大切にしてきたことは事実です。むしろそういった内発的な神道的宗教観と外発的に受容した宗教観(長い目で見れば仏教や一部のキリスト教の受容)のかけ合わせこそが日本の典型的な宗教観であるといえるかもしれません。
8. 日本の宗教事情の特殊性を鑑みた上で、研究成果を世界の宗教や信仰の状況の理解に敷衍することはできるのでしょうか?
今のところは、それができると信じて研究を進めています。もともと心理学の目標は人類に一般的に言えるような法則を見つけることだと思いますが、個人差や文化差がとても重要になってくる構成概念があります。
宗教もその最たるもので、キリスト教にせよ仏教にせよ死生観の提供や道徳的な概念の付与など共通する機能がある一方で、自己の考え方や世界の一貫性などの相違点を詳細に検討することが宗教全体の理解になると考えることができます。現在の宗教心理学の研究の多く(実に6割ほど)は北米で取られたデータに基づいているという調査がありますが、これが世界の宗教を正確に反映できているかはいささか疑問です。全く同じ研究を日本で行っても違った結果が出るということはよくあるので、文化差が見られたときにその違いを生み出すものを突き止めることでこれまでの研究に新しい視点を提供できると思っています。
9. 自然言語処理によるテキスト分析で、「宗教性」「スピリチュアリティ」「神聖さ」「神」という語に対して日本人が抱くイメージを検討される、とのことですが、具体的にどのような調査を行うのですか?ツール、サンプル収集方法、分析、対面・オンラインなど、差支えのない範囲でお聞かせください
特に欧米の宗教心理学の研究者は、「宗教性(religiousness/religiosity)」「スピリチュアリティ(spirituality)」「神聖さ(sacredness/the sacred)」という3つの言葉をよく使用します。例えば、宗教性とスピリチュアリティという言葉はアメリカ人にとっては一般の方でも弁別可能なもので、宗教は教義や宗教団体、儀礼などの伝統的な宗教活動に深く関連している体験を意味し、スピリチュアリティは信じる気持ちや大きな存在・力といった特定の宗教に依存しない個人的な体験を意味するそうです。
しかし、日本でこのような分類がされているかは疑問です。スピリチュアリティという言葉に関しては、スピリチュアリズム、スピリット、スピリチュアルなど微妙に意味の違う言葉と混同することも多く、胡散臭さや危うさのようなネガティブなイメージを持つ人も少なくありません。このような一般的に人々が考えている「素人概念」は非常に重要で、特に実験における教示や質問紙の項目の言葉遣いにまで関係してきます。そこでこれらの言葉のうち、例えば欧米でいうところのスピリチュアリティは日本語のそれと対応しているのかといったことや、そういった気持ちになるときの状況はどんなパターンに分類できるかといったこと、トピックモデル手法を用いて明らかにすることができます。
広い宗教・年齢サンプルのデータが必要なので、合計600人ほどからデータをとって、この手の分析が得意な同期と一緒に共同で研究を進めています。僕もNLP系の本を読んで学習したり、LLMについても最低限の知識は付けキャッチアップしています。
10. 歴史的に見て、 そして今現在も、戦争や他者の襲撃を始めとする多くの過ちを宗教が犯してしまった今、宗教はまだ、人の心を救うことができるのでしょうか?
今までの宗教が全く同じ方法で人々に意味を提供できるかはわかりません。ただ、例えばイスラム原理主義はイスラム教徒の大部分とは異なる考えを持っていること、福音派は政治的な問題と関連していることなど、宗教に関する事実を正確に認識することは大切だと思います。
最近は宗教だけにとどまらず、大きなラベル付け(例: 移民、女性・男性)やzero-sum的なパターン化(共和党vs民主党)によって世界を単純化して認識してしまうことが構造的に多いと思います。しかし、宗教も政治も人間が何千年もかけて作り上げてきた叡智でもあるので、学べることは多いと思いますし、困ったときに助けてくれる存在にもなると思います。
11. 研究成果を一般の人が享受できるようにするために、何らかのアウトリーチ活動の実施は予定されていますか?
academist以外だと中学生や高校生へのアウトリーチをしたいなと考えています。僕が所属する京都大学では、高校生に授業をする制度があり、インタラクティブな交流も含めて今の若い人たちや自分よりもう少し年齢が低い学生が何を考えているのかを知れることは僕にとってもとても貴重な体験になると思います。
12. 科研費 特別研究員奨励費の給付対象に採択された研究計画「スピリチュアリティの生起過程に係る心理・神経科学的検討―自己超越的感情に着目して」について、方法や分析、結果の発表方法など、差支えのない範囲でお聞かせいただけますか?
うちのラボは畏敬の念やマインドフルネスに関する研究をしているので、その流れで僕はスピリチュアリティの研究をしています。その中で既存の心理学的な手法だけではなく、脳科学的なアプローチや情報学的な手法を用いて多角的にとらえどころのないスピリチュアリティ概念を理解しようという研究プロジェクトになっています。論文は基本的に国際誌に投稿する予定ですが、学会発表は国内外含めて積極的に行っています。academistの活動報告では困難や葛藤も含めて研究のことをシェアしていますのでぜひのぞきに来てください!
13. 外国から移住する人が増える日本において、多文化共生を図り、そのより良い在り方を考え続けることは今後一層重要になるかと思います。林さんのご研究内容を一般の人にもわかりやすい言葉にまとめ、例えば外国人労働者を多く抱える企業主などまったく分野の異なる方に向けて発信されるご予定はありますか?
外国人の就学・就労支援を行っている団体さんや地方自治体さんと一緒に研究を進められたらうれしいです。僕の住んでいる地域は在日韓国人の方が多く住む地域でそういった人権問題に関心がある場所ですし、自分の父もタイで長年働いていて外国人として異国で働くことの大変さや文化の受容の難しさを体感しているつもりです。基礎的な研究もさることながらそうした応用にも今後は力を入れたいと思っています。
このあいだ大学院の友達が、日本に住む留学生が出展するアート展を開催して少し手伝っていました。普段は文章や言葉で表現することが多い研究者ですが、アートはより「全部」を抽象的かつ繊細に表現することができるので、こういったアート展の開催もすごく興味があります。
14. 今後の研究のご予定を差支えのない範囲で教えてください
実を言うと僕はアカデミアに残るかビジネスの世界に行くかまだ迷っています。僕の家系はアカデミアの人が一人もいませんし、父は生粋の営業マンだったり祖父は会社をやっていたりしていて小さいころからビジネスの話を聞いて育ってきました。といっても小さいころはずっとミッションインポッシブルのイーサンハントにあこがれてスパイになりたかったし、サラリーマンだけは嫌だ!みたいなよくある(?)気持ちを抱いていました。今になって、解像度の高くない願望だなあと恥ずかしくなりますが…。
ただ、いざアカデミアにいるとなんだか社会との距離が遠いと感じてしまうことが多くあります。なんというか、社会におけるイシューが何かをあまり意識せずに研究をしたり、もしイシューに気づきそれが自分の関心と近かったりしたとしても直接的な介入に乗り出さないところが距離感を感じるポイントだと思います。
アカデミアはいろんな社会活動の基盤を作るシード的ポジションとして重要ですし、何の役に立つかわからないぐらいの基礎研究の貴重さも十分に理解しているつもりです。ですから、これはもちろん良い悪いの話ではなくて、自分がどちらに興味があって強みを活かせるかという問題だと思います。
そう考えたときに、僕は身近な人たちが社会のイシューにダイレクトに取り組む姿勢を見てきたので、そちらにどうしても惹かれてしまうことがあります。それと同時に俯瞰的なレンズで情勢を把握しエッジのきいた研究をすることの魅力も感じます。ただどれだけビジネスに興味があるからと言って博士号を取得することに意味がないとは思いません。むしろ、博士号をとって小さい範囲でもある程度のエキスパートになることで、ビジネスに身を移した時に力を発揮できると思っています。
15. 林さんの研究活動の原動力やインスピレーションは何ですか?
僕は基本的には威勢のいいタイプの様に見えるらしいのですが、あまり人生の原動力がないタイプかなと思ったりします。両親には割と不自由のない生活をさせてもらってきたので、お金や業績のようなある種目に見える問題にあまり興味が示せず、どちらかというと本質的なことに向き合っていたいという気持ちがあります。
ただ、小学5年生でタイに移り住んだときに見た手足のない物乞いの人やアメリカの格差社会や希望の持てない先進国の現状を目の当たりにすると、どうも気が気ではなくてなにかアクションをおこしたいと感じます。宗教の研究をしているのもそれが多くの人の人生においてもっとも影響力のあるものだからです。お金も恋愛も人付き合いも死に方もモラルも幸せの形もすべて宗教に関連しています。宗教は世界の見方を提供するレンズなので、こういう本質的な問題に取り組むことで自分が解決したい多くの問題に貢献できると思えるので研究が好きなんだと思います。
それから今までの人生、運がいい方なので、100%努力せずともうまくいったり、王道ではない道を進むことで生存してきたという劣等感があるので、真正面から大変な博士号取得を通じて初めて自信の持てる自分のアイデンティティを手に入れたいと強く願っています。
16. 研究で行き詰まりを感じる時の対処法は?
行き詰まりしか感じません。プラクティカルな対処法は、インプットとアウトプット両方の整理をすることです。
インプットで言えば、別の分野に足を延ばしてみたり、別のレイヤー(例えばより抽象的な哲学書やより詳細なエッセイやツイート)からの情報を得たりするようにしています。それからまだ院生なのでボスの話は意識的に「素直に」聞くようにしています。僕は自分のボスが大好きで、研究はもちろんキャリアや人生のメンターとして認識しているので、自分のために自分が見えていないところまで考えてアドバイスして下さると思って、とりあえずボスに相談しています。
それからアウトプットに関しては、月並みですがお風呂やサウナに入ったり運動したりすることで頭の中を整理します。最近はローカルな銭湯に行ったり、そこのお客さんや商店街の人とお話したりもしてます。大阪に住んでいるとそういったコミュニティがまだ残っていますし、ご高齢の方からは面白い宗教小噺が聞けたりしてとってもいいです。
academistの活動報告のような、心理学的な研究を普段していない方にうまく研究を伝えようとすることもいい頭の運動になっていますね。また、文章を書いたり言葉で話す以外の方法でのアウトプット、例えばアートやイメージの制作も結構しています。研究は自分の気になることの一部を磨いて世の中に発信することだと思っている節があるので、研究だけでは伝わらないところまで伝えようとする本当に大事にするべきテーマが見つかったりするかなと思います。まだあんまり偉そうなことは言えませんが…
17. 日本の学術研究を発展させていく上で、社会に求められることは何でしょうか?
ちょっと批判を受けるかもしれませんが、「てきとーさ」みたいなものが雰囲気としてあれば嬉しいなと思います。
研究には長期的な目線でゴールを設定し、そのゴール到達のために必要であるお金を含む資源を惜しまないことが重要だと思います。しかし、研究はもともと、ギャンブルというか成功が予測しにくい投資だと思うので、税金からねん出された研究費の額に比べて社会を変えるレベルの研究が出てくる割合のようなパーセンテージが悪くてもある程度しょうがないことだと思ってくれたら嬉しいなと思います。
逆に、アカデミアももう少しリアリストになって、社会に自分たちが必要とされるようなパフォーマンスを惜しまないほうがいいかなとも思います。これは全員がそうするべきだということではなくて、例えばサイエンスコミュニケーターの方やRe:Relのような存在が、研究者の面白さと重要性を社会の中に伝播してくれることも考えられると思います。いわゆるマーケティング的な側面に注力することも重要なコミュニケーションかなと思う今日この頃です。
18. 最後に、博士課程に進もうか迷っている修士・学部生にアドバイスをお願いします
もちろん個人的な事情や金銭的な不安、社会的な風当りなど、博士課程を躊躇する理由はこの国には多くあると思います。多かれ少なかれ博士課程にいた人ならこれは理解できるはずですし、僕も日々感じます。
ただ、もし自分が本当に博士課程に行きたいと思うのであれば、その決断は決して間違いではないと思います。これは僕のボスの受け売りでもありますが、今後AGIやASIが完成されて身体的にも頭脳的にも僕らが太刀打ちできない時代が来れば、エキスパートや専門家以外はほとんど淘汰される可能性があります。その専門性がアカデミアでなくても勿論いいと思いますが、博士課程(もしくは研究)はだれも切り拓いたことない新境地に先人の知恵を借りながらがむしゃらに進むという修行です。そのあまりにもきつい博士課程を乗り越えれば、これからなにが起こるかわからない世界でフロンティを開拓していける下地が出来上がると思います。ですので、キャリアにおける運転免許証をとるつもりで挑戦してみてもいいのかもしれません。
もちろん、早いうちからお金を稼ぐことだって重要なことですし、ライフステージを考えると博士課程に進めないということもあると思います。僕はそれをリスペクトしますし、実際僕もパートナーには早く楽をさせてあげたいと思います。両親にも早く一人前の社会人の姿を見せたいし、飼っている犬にも最高級フードを買って毎日貸し切りドッグランに連れて行ってあげたいです。それでも、彼らはみんな応援してくれているので僕は頑張れています。
もし博士課程に入ると決断された方に一つお伝えできるなら、サバイブすることを一番の目標に据え置くことはおすすめかもしれません。博士課程に入ると、必ず自分よりすごい同期や一生かかっても届かなそうな先生や猛スピードで迫ってくる後輩に出会うと思います。でも、僕そしてあなたの目標は彼らに勝つことではなく、ちゃんとした研究をして博士号をとることだと思います。その博士号取得のために、どうしたら精神が擦り減らないか、体力が持つかを考えることは結構見逃しがちですし、だんだんおろそかになってくるポイントです。より多くの方が楽しく安全に道を切り開けることを願っています。(癒しが欲しい時は僕の犬の写真を見ましょう)
クラウドファンディングサイト「academist」の林さんのページはこちら。クラウドファンディングに挑戦する理由や現在取り組まれている研究課題についてお話しされています:
https://academist-cf.com/fanclubs/356
こんな記事もどうぞ
櫃割仁平氏へのインタビューー「美は世界を救う」を心理学で実証したい
渡部 綾一氏へのインタビューー意識の発達の多様性を解明し、子どもたちが生きやすい社会を目指す!