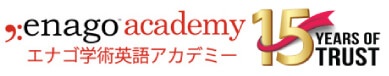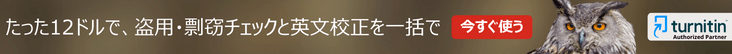櫃割仁平氏へのインタビューー「美は世界を救う」を心理学で実証したい

日本初の学術系クラウドファンディングサイト「academist」を運営するアカデミスト株式会社が実施する、若手研究者を対象とした研究費支援プログラム「academist Prize」。エナゴが協賛する同プログラム第4期の採択者でありアンバサダーでもある、ヘルムートシュミット大学 人文社会科学部 リサーチフェロー、日本学術振興会 海外特別研究員 櫃割 仁平博士に、書面インタビューでお話を伺いました。
1. 俳句という特定の詩の形式を対象として、様々なテーマで研究を行われています。いつごろ、どのようなきっかけで今の研究テーマに興味を持たれましたか?
初めて研究を行った卒業論文のテーマは「感動体験」に関するものでした。自分自身がいろいろな物事に感動しやすい性格で、その感動というものが人生に彩りを与え、成長していく鍵にもなっているのではないかと思ったからです。
ただ、「感動」の定義は広く、曖昧であり、大学院で研究していくにはもう少し絞ったほうがいいと考えていました。その結果が、アートや美の研究であり、俳句という題材でした。
2000年以降、アートや美に関する心理学の研究が増えてきたのですが、その主要な題材は、絵画などの視覚芸術や音楽でした。言語芸術の研究はまだまだ未解明要素も多く、そこに集中して取り組み始めました。その中でも俳句は、世界最短の詩であるので、美の核心に迫るためにいい題材だと思いました。物理学で原子、原子核、陽子、クオークなどとどんどん小さい世界を探求することで、真理に迫っていこうとする動きと近しいものを感じていました。
2. academist Prize 第4期でクラウドファンディングに挑戦中のプロジェクトについて教えてください
「美は世界を救う」を心理学で実証したい、というプロジェクトを進めています。「美は世界を救う」という言葉はロシアの文豪ドストエフスキーの言葉です。プロジェクトを立ち上げるまでの5年ほど美の研究をしていて、直感的にこの言葉に「たしかにそうかも」と思いました。それなら、本当にそうかを確かめるのが心理学者の仕事かなと思い、プロジェクト化しました。
心理学ではミクロに検証を進めていくことが多いので、まずは個人レベルで美が人の行動や態度、性格を変容することを検討したいと思いました。例えば、今準備中の研究の一つが、美が環境意識に与える影響を検討することです。ご存じの通り、地球環境が大きく変化していて、私たち一人ひとりにも行動変化が求められている点もあると思うのですが、そこに美が役割を果たしたらおもしろいなあと思っています。「地球温暖化が進むと災害が起こるぞ」と言われるよりも「地球温暖化が進むと、桜や紅葉を愛でることができなくなるぞ」と言われる方が行動を変えようと思えるのかなあという仮説を立てています。
また、このプロジェクトでは「コミュニティサイエンス」にも挑戦しています。プロジェクトのサポーターさんが集うオンラインコミュニティ「あいまいと」を作っていて、毎日活発に動いています。
私の研究進捗はもちろん、美や曖昧さをはじめとした私の研究テーマに近い情報共有(論文・書籍、イベントなど)、そして、実際にサポーターと一緒に行う研究プロジェクトも進んでいます。一つのプロジェクトに関して言えば、研究をしたことがない方と、仮説・計画を立て、データ収集・分析を行うところまで既に終わっており、論文を書いている最中です。
研究を進めてきた中で、「研究って研究者だけでしているのもったいなくない?」と思うことが増えてきて、狭義の「研究者」以外の方が日々感じている疑問や不思議、気づきを研究に昇華できる場所を作りたいと思っています。上述した「美と環境意識」の研究もこのコミュニティサイエンスの一環で立ち上がりました。
3. academist Prize 第4期にアプライした理由は何ですか?
激動のAI時代において、世界が一変するような変化が毎日のように起こっています。それは、研究という営みにも影響を与えており、これからの研究者はこれまでと全く違った形をしていると思っています。academist Prize 4期で目指している1000 True Fansを考え続けることがそんな新しい形の研究者になることに繋がるのではないかと漠然と考えていて、アプライしました。
4.「美」と「救い」という、一見かけ離れた二つのものをつなげたいと思った最初のきっかけはなんだったのでしょうか?
上述したように、これは、私の言葉というよりも借りてきた言葉なのですが、もう一つこのプロジェクトにしようと考えた理由は、自分の研究を社会と接続させたいと思ったところがあります。
美、特に俳句などの研究をしているとどうしても「何の役に立つの?」と思われることが少なくないと思います。個人的には、自分の「知りたい!」という気持ちで研究している部分も大きいのですが、それは、社会実装と関係ないということでもないと思っています。むしろ、これを考え続けることもお金を頂きながら研究している研究者の仕事だと考えています。そう考えたときに、ドストエフスキーの言葉と繋がり、上述したような研究を実際に行うところまで来たわけですが、これを言い始めた時は、具体的なリサーチクエスチョンまでは思いついていませんでした。とりあえず、大きなところから言い出してみることによって、少しずつやることが見つかってきた感があります。
5. 造形、立ち居振る舞い、あるいは思考回路など、「美しさ」を見いだす対象は多様です。その中でも「俳句」という「言葉の芸術」を対象に選んだ理由は何ですか?
上で書いたこととも少し重なりますが、言語芸術が視覚芸術などと比べて、研究がなされていないと感じたことが一番大きいかと思います。研究がなされていないと言っても、アリストテレスが『詩学』を出したというくらい伝統的なテーマのはずですが、対照的に、心理学などの実証的な研究は少ないままです。
この少ない理由はと言いますと、おそらく、物理的な対象物がないということが大きいと思います。テキストになっている文字を読んだり、その音声を聞いたりしても、頭の中で広がる世界は人それぞれです。その人それぞれ具合が実証研究を難しくしていると思いますが、私はそのチャレンジングな状況を面白いと思ってしまいました。
6. ドイツ ヘルムートシュミット大学での研究環境と、日本の研究機関での研究環境との間に違いはありますか?
私は日本の研究機関もたくさんは知らないので、一般化は難しいところもありますが、今のドイツの大学は時間を区切って研究している人が多いように思います。土日に働く人はほとんどいませんし、長期休みも研究から完全に離れて過ごしている人が多いです。また、ヨーロッパは隣国同士が近いこともあり、他の研究室とのコラボレーションも活発だと感じています。毎週のように、他国も含めた大学から、研究者が来たり、ボスや同僚が派遣されたりしています。私もそういったネットワークを積極的に作っていきたいと思います。
7. 欠かさずにチェックしている学術ジャーナルなどはありますか?最新の研究情報にアクセスする方法は、研究成果が発表される言語や国で違いはありますか?
Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Artsという学術ジャーナルは、研究を始めてから出た論文は、少なくともタイトルはすべてチェックしていると思います。あまり大きな違いはないと思いますが、ソーシャルメディアを通じて、日本人研究者仲間の成果を一番に目にする機会はあるので、そこから日本語の論文を読むことはあるかなと思います。ただ、これからは、海外の研究者ともどんどん繋がっていきたいので、そういった違いも少なくなっていくと思います。
8. 美に関する研究というと世間的には定性的な研究がイメージされるかと思われますが、櫃割さんは定量的な手法を取られています。同じ分野や近接した分野の研究方法(method)の潮流や、その中での櫃割さんの研究方法の独自性などがありましたらお教えください。研究方法の策定や、データ分析の上での困難などはありますか?
伝統的な心理調査や実験法を中心としながらも、MRIを用いた脳機能計測、瞳孔系測定やアイトラッキングなど神経科学的、生理的手法も導入していました。
また、最近ですと、AI技術の高まりにより、自然言語処理の精度もとても高くなってきており、研究手法に組み込んでいます。例えば、「どれくらい美しいと感じましたか?」と聞いて、「1. まったく美しいと感じなかった」から「7. とても美しいと感じた」という点数のつけ方をしていたのが、これまでのやり方でした。これからは、「この作品を見て感じたことを自由に書いてください」と聞いて、そのテキストを分析するということが可能になってくると思います。人のこころの複雑さをできるだけ複雑なままでとらえることができるのではないかと期待されています。
困難なことは、上で新しい分析について書いておきながら、数学や統計がそこまで強くないことです(笑)。 ただ、これからは、それこそAIをパートナーにしながら、そういった苦手なところも補っていけると考えています。
9. 俳句の曖昧さに関する研究では、実験の参加者を「クラウドワークス」で募ったとありますが、今後、ドイツ・日本で参加者の関わる実験を実施する場合、どのような方法で参加者を募り、どこでどのように実験を行う予定でしょうか?
これまで数回オンラインで文化比較を行ってきたのですが、その時は、日本人参加者は「クラウドワークス」さんで、そして、ドイツ人をはじめとした欧米の参加者は「Prolific」さんというプラットフォームで調査、実験を行うことが多かったです。
今もまさに進行中ですが、ドイツ人の同僚と共同研究で行う場合は、実験室にドイツ在住の日本人の方に来ていただくこともあります。日本人コミュニティにご協力いただくことによって、今のところは、集めたいデータ数が取得できています。
ただ、想像できるかもしれませんが、注意が必要なのは、日本に住んでいる日本人とドイツに住んでいる日本人でも特性が違う可能性がある点を考慮することです。ドイツ在住歴や渡航した年齢を尋ねて、統計解析の際に影響を除外したり、結果を解釈する時に、過度な一般化を避けたりする必要があると思います。
10. ご自身のウェブサイト、X、音声で発信するVoicy、また今挑戦中のacademistでのクラウドファンディング、さらに色々な分野の方とのコラボレーションを通じて、ご自身の研究活動について積極的に発信されています。櫃割さんが、研究者として、「不特定多数のクラウド」という情報の受け手に見いだす可能性は何でしょうか?
私は、心理学をはじめとした「研究」や「科学」というものが心底おもしろいと思っています。発信をすればするほど、おもしろい研究や研究者、研究に関わらず様々な情報を知れる機会が増えるとも思っていて、発信をしているところがあります。また、このおもしろさというのは、何も研究者だけのものではないと思っていて、研究に携わったことがない方も含めて、一緒に楽しめたらという気持ちで発信しているところがあります。
11.「曖昧なままそよぐ」という櫃割さんのキャッチコピーについてお伺いします。2018年から2022年まで、Teacher Aidという学生団体を代表として運営されていました。その頃から、「ゆるさ」や「自然に生きる」という、同キャッチコピーにつながる思想をお持ちだったかと思います。「定まらないもの」や「やさしいもの」に魅力を見出した原体験があれば教えてください。
たしかに、言葉は違えど、大切にしているものは前からあまり変わっていないかもしれません。
一つの原体験というわけではないと思いますが、強いてあげるとすると、ニュージーランドでのワーキングホリデー生活は大きかったと思います。ニュージーランドで出会った人たちと話したり、国の制度の違いに気づいたりする中で、もっとゆるやかに生きたら幸せじゃないかと思うようになりました。特に、当時は中学校教員を志していたのですが、学校の先生の働き方が日本とあまりにも違っていて衝撃を受けました。「子どものためなら自分を犠牲にしてでも働く!」と思っていたこともあったのですが、ニュージーランドの生活以降はその考え方は180度変わったと思います。
12. 人の心を研究し原理を解明するだけでなく、人の生きやすさを後押ししたり、より良い社会の実現を提唱したりする、心理学という研究分野の魅力を教えてください
心理学の中でも実験心理学と呼ばれるデータや統計をもとにした心理学を専門にしています。もちろん、人のこころの複雑さを考えるとそのすべてを数値化することはできないのですが、それでも代替的な指標を使って、数値、そしてビジュアル化することができるのは、心理学の強みだと思います。
また、心理学には、教育心理学、発達心理学など、○○心理学とつく細分化された分野があります。これは、ほとんどあらゆることに適応可能で、それだけ、様々な事象に人のこころが関係しているということだと思います。
自分が気になること、もしくは、社会に影響を与えたいことがあったときに、多くの場合、心理学はそこに研究テーマを用意してくれているはずです。そして、その研究を進めた先に、数値とビジュアルをもって、多くの人に届け、対話していく力を持っていると思っています。私も美というとらえどころのない概念と向き合っていますが、データとグラフがあることによって、議論がしやすくなっているなあといつも感じています。
13. 倍率10倍以上、博士課程の最高峰とも呼ばれる「日本学術振興会 育志賞」の第14回を受賞されました。おめでとうございます。ご自身の研究が選ばれた理由は何だと思いますか?
ありがとうございます。大学院時代は指導教員の先生をはじめ、本当に周りの方々に恵まれていたと思います。それが大きな要因と思います。先生が研究の楽しさを教えてくださり、俳句という題材も先生とのディスカッションから生まれたものでした。また、先輩方や周りの同期も研究を楽しみながらも、成果を出し続けている方々ばかりで、私の中での研究水準を高めてくださったと思っています(例えば、私がM1の時の博士課程の先輩が同じく育志賞を受賞されていました)。他大学から進学したので、最初は付いていくのが精いっぱいでしたが、背中で進む方向を示すと同時に、研究の悩みなどを細かく聞いてくださった方々に感謝しています。
14. STEAM教育におけるArts(芸術・リベラルアーツ)の役割は何でしょうか?ArtsはSTEMでの創造や成果に貢献するもの、という位置づけなのでしょうか?
Artといってもあくまで思考法や世界の見方のことを言っていると思います。合理的ではないことも含めて、個々人の内なる感情や信念などを持ち、表現しようとする態度のことなのではないかと考えています。そういう意味では、STEMでの創造や成果に貢献するものというよりも、創造や成果を生み出す源泉的なものではないかと思います。STEMはその創造や成果を助けてくれる存在ではないでしょうか?
ただ、この数年で言葉の意味合いもそれらの関係性も変わっていくかもしれません。ご存じの通り、AIの存在は、STEMの力を多くの人に与えてくれていると思います。ただ、Artの思考法や世界の見方は教えてもらうことができず、人それぞれが持っているものだと思います。ますますArtの重要性が増していくのではないかと考えています。
15. 今後の研究のご予定を、差支えのない範囲で教えてください
これからは俳句だけでなく、芸術のジャンルを広げつつ、文化比較の研究を中心に行っていく予定です。現在取り組んでいるのは、雅楽の舞や書道で、これから取り組みたいのは、生け花の鑑賞研究です。どれも日本的な題材を使用しています。
これらはばらばらの題材に見えますが、私が突き止めたいのは、より普遍的な美の法則です。これらの研究を蓄積して、数年後に、文化的経験美学 (Cultural Empirical Aesthetics) の理論を提案したいと思っています。まだまだ欧米の研究がほとんどの中で、文化的な視点を取り入れた理論やモデルを作り、さらに検証していくことが求められていると思います。それを中心になってやっていきたいです。
16. 櫃割さんの研究活動の原動力やインスピレーションは何ですか?
「楽しい」が原動力な気がします。新しいことを知る時、新しいことを知ろうとしている時、楽しいなあと感じていて、その瞬間をたくさん味わいたいと思っています。
インスピレーションは、人と話す時に得られることが多いと思います。Voicyというポッドキャストプラットフォームで週に2回程度、対談企画を行っています。心理学者のこともあれば、Voicyパーソナリティのこともありますが、ひょんなきっかけで縁のあった方とお話しする時もあります。人と話していると、「あ、これもやってみたいなあ」と思いつくことが多いような気がしています。
17. 研究で行き詰まりを感じる時の対処法は?
やりたいことがどんどん出てくるので、行き詰まりを感じたら、別の課題に取り組むようにしています。私のこれまでの研究は、美や芸術に関することが中心にありながらも、宗教性、投資、サウナなど、トピックが多岐に渡っており、一つのテーマで行き詰まっても、他のテーマを進めることができました。ただ、行き詰まり続けて、お蔵入りしそうなデータもあるので、気を付けないとなとも思っています(笑)。
18. 日本の学術研究を発展させていく上で、社会に求められることは何でしょうか?
あまり思い浮かびませんでした。強いて言うなら、研究者ともっと関わっていただけたら嬉しいなあと思います。しかしながら、これを言うなら、まずは私も含めた研究者がもっと社会とコミュニケーションを取ろうとするのが先だと思っています。市民の方々と研究者の対話の機会が増えれば、研究の重要性や面白さが伝わると思いますし、そうすると、研究にもっとリソースが回っていくような社会になるのではないかと思っています。
19. 最後に、博士課程に進もうか迷っている修士・学部生にアドバイスをお願いします
博士課程での研究、本当に楽しかったです。純粋に研究を楽しむと同時に、ドライに使わせていただけるものはしっかりと使わせていただくという姿勢が大切だと思います。最近は、学振以外にも博士課程向けの研究費が増えてきていると思いますし、私がやっているようなクラウドファンディングの仕組みも一般的になりつつあります。それらをうまく活かして、楽しく研究できる環境を少しずつでも作っていけると思います。私も新米の研究者として、みなさんにやり方の一つを提示していけるようにがんばりたいと思います!
クラウドファンディングサイト「academist」の櫃割さんのページはこちら。クラウドファンディングに挑戦する理由や現在取り組まれている研究課題についてお話しされています:
https://academist-cf.com/fanclubs/358
こんな記事もどうぞ
渡部 綾一氏へのインタビューー意識の発達の多様性を解明し、子どもたちが生きやすい社会を目指す!
土田亮氏へのインタビューー個々人が意思をもって災害復興できる社会の実現を目指して