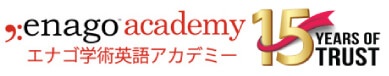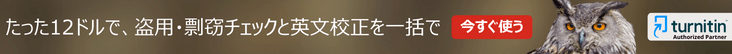渡部 綾一氏へのインタビューー意識の発達の多様性を解明し、子どもたちが生きやすい社会を目指す!

日本初の学術系クラウドファンディングサイト「academist」を運営するアカデミスト株式会社が実施する、若手研究者を対象とした研究費支援プログラム「academist Prize」。エナゴが協賛する同プログラム第4期の採択者でありアンバサダーでもある、京都大学大学院文学研究科渡部 綾一博士に、書面インタビューでお話を伺いました。
1. 心理学や発達科学など分野を横断する学際的な研究を行っていらっしゃいます。いつごろ、どのようなきっかけで今の研究テーマに興味を持ちましたか?
意識の発達研究を始めたのは、大学院に入ってからですが、ぼんやりと意識の発達に興味を持ち始めたのは、小学生のころからです。私は当時、自分の行動や感情をコントロールできない子どもで、いつも怒られて、泣いてばかりでした。自分の思考や行動なのに、自分では思い通りにならないことに苦しんでいました。同時に、苦しんでいることを周りの人に理解してもらえないことに、疎外感を感じていました。それから「私とは何か」「生きるとは何か」「世界とは何か」を考えるようになりました。そのヒントが、意識と発達だと思って、今の研究テーマを始めました。
2. 意識の発達に関わる研究活動の魅力はどのようなところですか?
研究活動の魅力はいろいろありますが、大きく2つあります。
1つは、意識の不思議な現象や子どもの反応が、純粋に面白く魅力です。私は、バックワードマスキング現象という、意識の現象を利用した実験をしてきました。こういう実験から、私たちが意識している世界と現実の世界が少し違うことがわかってきました。また、子どもたちは私たちの予想を超える反応をしてくれます。そういった、体験が魅力です。
もう1つは、この面白さを他の人に共有できることが魅力です。こんなにおもしろい世界があるよ、ともっと多くの人に知ってほしいです。意識はまさに生きることの不思議・面白さですし、子どもは子育ての不思議・面白さにつながります。生きることや子育てをサポートする知見やモチベーションにつながったら嬉しいなと思い、研究活動をしています。
3. academist Prize 第4期でクラウドファンディングに挑戦中のプロジェクトについて教えてください
私が研究を通して成し遂げたいことは、意識の発達の多様性とその認知神経基盤を明らかにすることです。
これまでに私は、幼児・児童期の子どもの視覚的意識の発達に関する実証研究を行ってきました。今後の研究では、多様な背景の子どもたちを対象に、視覚以外の知覚的意識、自己に関する意識、意識の発達の多様性の解明にチャレンジします。世界でも前例のない研究テーマです。このプロジェクトは、私の大きな研究テーマへのチャレンジの最初の一歩です。現在は、研究テーマに関係することの事前調査と実際に定型発達の子どもと成人を対象に、視覚と聴覚の意識の実験をしています。研究の途中経過をサポーターの皆さんに共有して、一緒に研究を進めています。
4. academist Prize 第4期に挑戦した理由は何ですか?
私がacademist Prize 第4期に挑戦した理由は、意識の発達の多様性を多くの人に知ってほしいからです。社会や大人の勘違いや知識不足によって子どもが理不尽に怒られ、傷つくことを減らしたいと思っています。
また、若手研究者が研究しやすい環境を同じ志を持つ同志と共に作り上げたいからです。大学院生やポスドク研究員は研究費や生活費の獲得に苦労することが多いです。私も、1年ごとの契約のポスドク研究員であり、生活は安定していません。このような状況では、創造的な研究は難しいです。若手研究者が研究に専念できる機会と期待を生み出していきたいです。
5. 研究の対象となるのはどのような人々でしょうか?
意識の発達研究の試みは、世界中でも新しいので、研究が少ないです。まずは、大多数の人の意識の発達の傾向のデータが必要です。そのため、定型発達の子どもと成人の研究から始めています。
次に、比較的研究の積み重ねがある発達障害に関する研究を推薦者の先生方と進める予定です。段階を経て、外国にルーツを持つ子どもも含め、さまざまな子どもたちを対象として、発達の多様性研究を広げて行く予定です。このクラファン活動中に、共感覚の生きづらさや意識に関する情報の提供がありました。活動を通して、協力者も集めていきたいと思っています。
6. 子どもおよび成人の被験者を募る際、および被験者を対象とした実験を実際に行う際の困難や、今後想定される課題などがあれば教えてください
まず、子どもの参加者のリクルートと実験実施がとても大変です。子どもおよび保護者の皆さんに調査参加の依頼をするために、子どもに関連する施設に参加協力のお願いをしたり、町や民間の掲示板で募集をしたり、一人一人に電話をかけたり、と時間と掲載費、謝金などがかかります。
保育園・幼稚園、小学校に通っている子どもの場合には、大学での調査には、平日は忙しいため、休日に来校してもらうことになります。また、発達の多様性の調査のためには、発達に特性がある子どもたちに調査を依頼する必要があります。また、調査参加の負担も大きくなり、調査自体が成立しなくなることが予想されます。子どもの調査では、調査を最後まで行ってもらうことにも難しさがあります。そのために、成人に比べて、簡略化し、多めに参加者を見積もる必要があります。
7. 研究成果を社会(大人)にアウトリーチすることで、社会(大人)の勘違いや知識不足の是正を目指されているとのことですが、小学生や中学生に向けたアウトリーチを行われるご予定はありますか?
小学生や中学生、高校生、学生を含めすべての方にアウトリーチしたいです。小中高校生が通う塾や高校でも、意識の発達や多様性についての講演をさせてもらっています。
難しいところが、小中学生くらいだと、内集団に敏感になったり、同質性を求めたりする傾向が少し強いので、理解と行動の乖離が発生しやすいかもしれません。意識の発達の多様性に気づいて、理解してもらい、子ども同士のいじめの減少や不登校の理解に貢献できるように活動をしてきたいです。
8. academistのウェブページ内で、「研究を通して成し遂げたいこと」を「すべての子どもが生きやすい社会にしていきたい」との言葉で結ばれていますが、意識発達の多様性の理解促進が、大人たちや社会全体に資する(と期待される)事柄があれば、お教えください。
社会的に弱い立場になる子どもが生きやすい社会は、大人にとっても生きやすい社会であると私は考えています。もちろん、大人には大人特有の子どもとは違った生きにくさがあると思いますが、意識の発達の多様性の受容は、生きるうえでの最低限の安心感に繋がります。子どものときに体験した生きづらさに苦しむ大人は多いと思うので、その予防にも繋がります。
9. 渡部さんの描く「生きやすい社会」とは、どのような社会でしょうか?
理不尽を感じることのない社会です。生きづらさは、自分と他者、社会のギャップにあると考えています。他者と違うこと、自分の理想と違うこと、社会が求めていることと違うこと、自分とは違う基準に合わせること、合わせることを強いられること、合わせられないこと、などに理不尽さを感じ、自分あるいは他者、社会を責めざるを得ない、そういう状況に理不尽さを感じると思います。違うこと、できないこと、を認められることに、生きやすい社会へのヒントがあると私は考えています。
10. 今後の研究のご予定を、差支えのない範囲で教えてください
上でも回答しましたが、調査対象を広げて、より大きく意識の発達の多様性を研究していく予定です。
今注目しているのが、感覚や認知の時間処理機能・能力と感覚過敏・鈍麻です。目や耳から入った情報において、何がどんな順番でどこにあったか、という、”なに、いつ、どこ”の処理精度や速度に、発達の多様性をひも解くヒントがあると考えています。年齢差や発達障害との関係も指摘されています。また、こういった感覚や認知の時間処理能力と”わたし”という自己がどのように関係しているのか、についても研究を考えています。
11. Monash UniversityにVisiting Researcherとして滞在された時の経験について教えていただけますか?また、研究者が海外の研究環境を経験することの利点は何でしょうか?
大学院博士課程の間に半年間、オーストラリアのモナッシュ大学で訪問研究員をしました。日本学術振興会の博士課程大学院生向けのプログラムである若手研究者海外挑戦プログラム採用者でした。
大学の近くのMonash Biomedical Imagingという研究所に滞在して、意識や神経科学の研究をしている研究室・研究者と交流することができました。また、滞在中に、Funding Consciousness Research with Registered Reportsという海外の研究助成金の申請にもチャレンジし、採択されました。日本を超えて世界に研究の視野を広げることで、研究費獲得や共同研究のきっかけや成功、研究者とのネットワークは格段に大きくなります。
また、研究者の働き方にも衝撃を受けました。土日は研究所にほとんど人はいなく、電気が消えていることが多かったですし、金曜日の午後にはすでに、ほとんど人がいなくなっていました。家庭や趣味といった仕事以外の時間を大事にできる仕事環境も大事であると学び、それ以降私も日本に帰ってから、仕事も大事ですが、趣味や恋人、家族との時間も大事にするようになりました。
12. 研究者が英語での発信力を向上させるためのアドバイスはありますか?
研究者にとって、発信内容が一番重要で、英語は道具なので、気にせずたくさん発信するのが良いと思います。最近では、翻訳ツールが多いし、精度も高いので、私は積極的に使っています。
13. 渡部さんの研究活動の原動力やインスピレーションは何ですか?
自分が経験した嫌なことや困ったこと、生きづらさを他の人には経験してほしくない、という気持ちで活動していることが多いです。科学や技術はそのような改善を積み重ねる営みであるとも考えています。特に子どもの時に経験した大人とのわかりあえなさ、わかってもらえない悲しさ、をなくしていきたいという気持ちが原動力です。分かり合えなさの根本にある認知や知覚、意識の違いを考えることが研究内容のインスピレーションになっています。
14. 研究で行き詰まりを感じる時の対処法は?
生き詰まったときは、研究テーマを基礎研究と現場のそれぞれの視点から考えたり、それぞれの領域の人と話したりするようにしています。学術的にどのように研究が積み上げられてきたのか、といった概念的定義や実験方法に頭が固まってしまうと、自由さが限られてしまいます。また、社会的にどんな問題があるのか、実際の子どもたちはどうか、といった現実から考えてしまうと関連要因が多すぎてしまいます。基礎研究と現場の視点のバランスをとることが大事だと思います。
15. 日本の学術研究を発展させていく上で、社会に求められることは何でしょうか?
個々の研究・研究者への興味と時間のかかることへの理解が社会には必要だと思います。基本的に、やる意味のない無駄な研究はないと思います。なにかしら意味や何かとの関係はあるはずです。もちろん研究者側が匙を投げてはいけないと思いますが、目先の利益だけを考えるのではなく、その研究の長期的な可能性を研究者と社会がともに広げていけると良いと思います。
16. 最後に、博士課程に進もうか迷っている修士・学部生にアドバイスをお願いします
ヒトは迷う生き物です。どうか迷ってしまう自分、予定通りにできない自分を責めすぎないようにしてください。それが研究の醍醐味だったりします。
研究や博士課程は大変なこともありますが、楽しいことややりがいもたくさんあります。生存者バイアスではありますが、わたしは博士課程に進んで良かったと思っています。私が博士課程に進むうえで大事だと思うことは以下です。
自分だけでなんとかしようと思わず、信頼できる他人を巻きこんで、できる限りの準備をしましょう。万全の準備をしていても、世界は予想外のことが沢山起きます。だから、できる限りの準備をしたなら、家宝は寝て待て、です。
信頼できる他人を見つけるために、研究室や指導教員、共同研究者選びはとても大事です。博士号取得は指導教員で決まると言っても過言ではありません。
できる限りの準備をして、だめだったら、それはしょうがないですし、あなただけのせいではないです。できる限りの準備をしたら、失敗でも次につながる学びがあるはずです。失敗を恐れずに、チャレンジしましょう。失敗したら、反省して・修正して、またチャレンジしましょう。博士課程はその繰り返しです。楽しくハッピーに研究しましょう。
クラウドファンディングサイト「academist」の渡部さんのページはこちら。クラウドファンディングに挑戦する理由や現在取り組まれている研究課題についてお話しされています:
https://academist-cf.com/fanclubs/357
こんな記事もどうぞ
櫃割仁平氏へのインタビューー「美は世界を救う」を心理学で実証したい
土田亮氏へのインタビューー個々人が意思をもって災害復興できる社会の実現を目指して