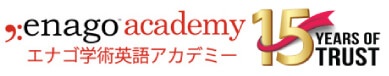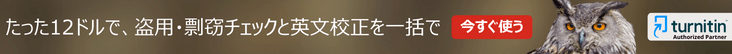土田亮氏へのインタビューー個々人が意思をもって災害復興できる社会の実現を目指して

日本初の学術系クラウドファンディングサイト「academist」を運営するアカデミスト株式会社が実施する、若手研究者を対象とした研究費支援プログラム「academist Prize」。エナゴが協賛する同プログラム第4期の採択者である、東京大学大学院総合文化研究科 超域文化科学専攻 日本学術振興会 特別研究員 土田 亮博士に、書面インタビューでお話を伺いました。
1. 被災者の声に耳を傾けて、個人の意思に基づいた行動や、国・自治体のより良い選択を促す研究を行っていらっしゃいます。いつごろ、どのようなきっかけで今の研究テーマに興味を持たれましたか?
博士課程の研究で、コロナ禍を経ながらもスリランカで災害復興と日常を調査してきて、無事に博士号をとりました。今後スリランカに加えて日本でも地道にフィールドワークをしたいなと考えていた時に、能登半島地震が起きました。その時は実家の宮崎に帰っていて、夕方以降にニュースを見て深く動揺してしまいました。学位を取ったり、論文を書いたりしてきたからって、結局こういうときに何ができるんだろうか、と冷笑的になりながらも、真剣に向き合うなかで自分の心に深く鋼鉄の杭が刺さったような時間を悶々と過ごしていました。
今のテーマに関して明確に意識し出したのは、2024年の2月ごろだったかなと思います。先の年始から、何かしら関わりをもつことができないか、どのような形が望ましいのか、ということをSNSやニュースを中心に探索していたら、諸々の反響を目の当たりにして、結局自分自身が燃え尽きてしまいました。「被災した地域や人たちの方がもっと苦しんでいるのに、どうして私がこんなに……自分ってこんなに弱かったのかな」と考え詰めてしまうことが、さらに苦しみを重くしました。あまりこの時の記憶もおぼろげで、必要最低限の移動や仕事以外は、ほとんど自室で塞ぎ込んで、何をしたかもよくわからないような気がします。それくらい傷ついてしまったんですね。
鬱屈になって、情報や人から離れて一人で考え込んでいる時に、ふと「私は誰の声を聞いていたんだろう、どういう立場でいたい、関わりたいのだろう」と考えたんですね。「行かなきゃ、誰がどんな声で話しているのか、わからない」と。そして、自らとらわれてしまった声を一旦振り切って、まずはそこで暮らしてきた人々や現場で活動を行う人々の声を聞こう。その声をたよりに、不器用ながらも手を差し伸べられるようになるためには、自分が何者かを身体の経験から知らないと、何も答えは出ないと気づいたんです。
そういった混沌や苦しみのなかで、災害がもたらす苦しみを他者と共有・理解できない中で、いかに私たちは互いに傷や悲しみ、苦しみに関わり合えるのかという問いや、ボランティアやケア、語ること、聴くことによって互いにどんな生活があったのか、どうやって支援することができるのかといった、自己犠牲や解釈を施しながらも、いかにカタストロフィのさなかや新しい日常に向かう復興の時間のなかで、自ら生きていることや過ごす日々、選択、葛藤、決定を肯定できるのか、という問いが、普段は意識しないけれども、災害を通してふつふつと湧き上がってきました。
これらの問いを現場にコミットしながら探求していきたいという想いから、少しずつ心を取り戻し、身体も元気になり、フィールドワークとボランティア、聞くこと、記録することを始めました。
2. academist Prize 第4期でクラウドファンディングに挑戦中のプロジェクトについて教えてください
現在挑戦していることは、いかにして被災した人びとが生活を取り戻すのか、というプロセスを実践することと、記録することです。
前者の実践については、自らボランティアやフィールドで出会い少しずつ信頼を築いてきた人たちに互いの近況報告や訪問などといったかかわりを通して、実際に生活を別様の形で取り戻すということはどういうことなのか、その葛藤や選択のプロセスを多様なアクター(関係者・当事者)の観点から知ることです。
後者の記録については、もともとの生活から被災して、そして復旧復興、さらに新たな日常へ向かうことを間近に感じ、それを見届けることが、互いにどんなまなざしをもたらすのかをねらいにしています。
それを、被災の有無、世代、仕事柄、住まいの場所を問わず対話する場を作り、いつか災害が自分たちの生を揺るがすということがいかなることかを想像し、そこから方向づける生き方を再創造することができればと考えています。
別のインタビューでそのねらいについて長く語っているので、ぜひそちらも併せてご覧ください。
https://note-infomart.jp/n/n5e6f0e12fa84/
3. academist Prize 第4期にアプライした理由は何ですか?
多様なアクターと協働することに挑戦したかったからです。コロナ禍を経てどうにか博士号を取ってからは、ありがたいことに生活や研究の糧を得ることができ、教育や研究などの実績をコツコツ積み上げたり、フィールドワークに通ったりする時間も得ることができました。
しかし、それを仕事やその関係の仲間としてだけで閉じ込めちゃうのは、ちょっと寂しいなと感じたんですね。本当は、研究とか仕事とかフィールドワークとかに関係なく、じっくり時間をかけてそこにいる人の話に耳を傾けていたいし、そこで私自身も知らないことや驚き、悲しみ、喜びに触れていたいんです。それを自分だけにとどめず、これまで関わってきた人たちに広げることを通して、災害や復興に向き合うとはいかなる問いを投げかけることであるのかについて、共有しながら考えてみたかったんです。
それを、単純に国や民間の研究費でチームやプロジェクトとして短期で立ち上げ、解決して解散するのではなく、みんなと関わりながら中長期で災害や復興について考えるプロジェクトを進めていくには、こうしたクラウドファンディングは適切な形のひとつかなと考えました。
また、今academist Prizeの同僚である渡部くんや櫃割くんの過去のクラウドファンディングをSNSで側から見ていたり、途中支援に関わったりした際に、真剣に熱意をもって還元してくれている様子にすごく感動したことも、実はアプライした理由の一つです。
一人一人に感謝を示すようなコミュニケーションや、何をやっているのか、そしてそれを通して社会にどのように還元しようと考えて行動しているのか、という点を大切にしています。同年代の人たちが少しずつ研究と社会の形を変えようとしているのを見ていて、ならば、私も今できることをやってみようと思い立ったんです。
4. 海外でのフィールドワークの地としてスリランカを選んだ背景を教えてください
本当に偶然の積み重ねです。初めてスリランカを訪れたのは、学部3年生当時福岡県が主催で行った国際協力リーダー育成プログラムに参加したことでした。そのフィールドサイトがスリランカで、民族紛争や津波災害後の復興、家畜と生業、ゴミ処理、小学校教育、湖の水質改善など、国際協力の現場を肌で感じるなかで、実際に話をしたスリランカの人たちが、とにかく温和で魅力的で温かい心を感じさせてくれました。コミュニティセンターの開設式で、テンビリ(キングココナッツ)のココナッツウォーターを飲みながら、タミルのおばあちゃんと地域の未来について話したことも、すごくよく覚えています。
それからずいぶん時が経ち、大学院に入り、それまでの専門から災害研究に転向しようと志した際、当時の指導教員に「災害について研究するなら自分でフィールドを見つけなさい」と言われ、修士のはじめはとにかく焦りました。焦りを感じていた時、Facebookのタイムラインで、先のプログラムでお世話になったスリランカのおじいちゃんによる「スリランカで大洪水が起こっている。寄付が欲しい」というポストを目にして、寄付をしたんです。当時のプログラムでは行っていなかった地域だったけど、すごく関心があるなと思いつつ、学業が忙しくなって深掘りするのを躊躇してしまいました。
それから半年経って、そのおじいちゃんに「久しぶりに会わないか」と声をかけられ、彼が住んでいる福岡に久しぶりに会いに行ったら、「土田くん、フィールドサイトで困っているんだったら、スリランカであの時寄付した地域で研究したら?」と言われたんです。「はっ、そりゃあそうだな」と、ご恩と縁を感じて決めた、という流れなんです。
そうと決まってその時の災害を調べると、確かに2017年の大洪水によって、スリランカが急激に災害リスクと脆弱性の高い国として国際的に位置付けられるようになり、国際でも国内でも大きな支援等の動きが目立ったこともありました。おじいちゃんの知り合いを通して出会った地域行政の方々や、都市計画のプランナー、街をぶらぶらして出会ったいろんな人たちに聞けば、この街は2017年のみならず、ほぼ毎年大なり小なりの洪水を受けている街であることがわかりました。直観的に、そんなに災害が起こる街なら住まないほうがいいだろうに、どうして、どうやってこの街に住んでいるのか?そうした出会いと問いが気になって、フィールドワークを始めました。

2017年5月末にスリランカ・ラトゥナプラ市内で起こった大洪水の様子。1階が完全に水没している。(撮影:土田氏)
5. これまで行われたスリランカでのフィールドワークと、日本各地でのフィールドワークを振り返り、国や地域を跨いで共通して得られた洞察や、逆に、災害からの復興に関して地域特性のあることがらなどはありますか?
当たり前のこととして、国や地域を越えて何らかの枠組みから比較してみようとしても、同じ災害復興なんてないわけです。私たちはついつい文化や社会、環境、制度の違いに還元して簡単に説明しようとするときもあるんですが、はたしてその違いって具体的になんだろうか、何が関わっているから違うといえるのか、と最近ふと考えることがあって、それを追いかけています。
地域特性というと、日本のことはフィールドワークを通してまだきちんと身をもって理解しきれていないので深く言及できません。スリランカであれば、いかに各人が多層的なつながりの網目のなかで生きているのか、ということが災害からの復興に大きく関係しているのだと思います。
特に、経済大都市であるコロンボから山側に離れた、都市でも田舎でもないラトゥナプラと呼ばれる街が私がフィールドワークを行った場所です。そこでは家族を中心としたケアを回すために、親族や血縁が同じ地域に集まって住まうことが伝統的な規範として当時はまだ残っていました。同じ地域のなかで親戚や家族がたくさんいるんです。
インタビューするなかで、血のつながりと住まいの場所をマッピングすると、徒歩圏内か、バイクやバスで10分以内のところに住んでいる家族も複数ありました。その関係性の中で生きていくと、血縁も地縁も地域のなかでゆるやかに混ざり合っていきます。
また、スリランカは仏教、ヒンドゥー教、キリスト教、イスラム教など多宗教国家でもあり、街のいたるところにお寺や教会、モスクなどの宗教施設も点在しています。
そして、洪水が来そうな時には、この多層的なつながりが基盤となります。避難の際に、衣服や家具家財を近所の2階以上の家に動かして置いたり、プールのように水が浸かった地域を、地域のあちこちにあるボートを使って逃げ遅れがないか確認し救助したりします。宗教施設には、国のいたるところから寄付で毛布や食料などが集まります。さらに、被災してしまい、より貧窮にあえいだり、家の増改築を検討したりする際には、地域や親戚らが少しずつお金を出し合い、助け合おうとする場合もあります。一見当然のように思えるつながりは、地域と家族の歴史との連続性や関係性の網目のなかに生きることで生成されていることをフィールドやお話から学びました。
6. 将来自分が被りうる被害や現在他者が置かれた状況への想像力、自然への畏怖、被災者への利他的な行動などは、どのように相関するのでしょう。またそうした想いや知恵、アクションを何らかの方法で結びつけ、災害への備えや災害からの復興をより上手くできる社会づくりをすることは可能だと思われますか?
その出来事や主体は、「この私でもありえたかもしれない」という倫理的な探究や想像力と結びついてくるのかな、と思います。情報や状況に流されず、むずかしさやわからなさにじっと静かにとどまることが重要ではないかと思います。
それは、単に他者に向けて「そうなんですね」と素早く共感やレスポンスを促すのではなく、自らの中で渦巻いている不思議を携えながら、眼前にあったり、不可視化されていたりする何らかの存在を知ることが基盤になります。存在から知ることを通して、人による助けるという行為の根源やモラルについて手足で考えてみることです。
そうしたリアリティに、ぐっと、時折おずおずと近づいてでも考えてみることが、アクションや社会づくりの議論、方向性をより豊かにできるのではないかと考えます。
7. 石川県、佐賀県、宮崎県でワークショップの実施を予定されています。各ワークショップでの対話の内容を、被災地以外の地域に住む人たちにどのように発信していきますか?
具体的にこうしようということはまだ決まっておらず、じっくりと協働できる仲間と中身を相談していこうと思います。実は、今いろんな写真展やワークショップに自ら赴いて、写真家や経験者のお話をじっくり聞き、展示の仕方やファシリテーションなどを勉強しているところもあり、少しずつ方法や目的、対象を考えています。先日も、さまざまな人のご協力があって、スリランカでのフィールドワークや人類学的な思考を立ち上げる展示会を開くことができました。こだわった工夫やデザインを行なったなかで、さらに来場していただいた人から生のフィードバックをいただき、「なるほど!」と実感することが多くありました。これは調査だけでは得られない感性ですね。そうしたことを取り入れて発信や対話、展示、ワークショップを行いたいです。

「 展示でフィールドワークする スリランカ編2025」(東京外国語大学、2025/2/17-3/2)開催模様(撮影:土田氏)
8. フィールドワークで採用されている「聞き書き」の手法についてお話しいただけますか?撮影機材や録音機材の使用や、書き起こし、翻訳の方法などについても具体的にお教えいただければ幸いです
機材に関しては、特に変わった技術はありません。ボイスレコーダーを使っていますし、あるときはスマホで録音することもあります。できれば綺麗に音声をとりたいので、机などの物体と直接干渉しないように、レコーダーの下にハンカチやタオルを置いています。
聞き書きにもさまざまな作法やこだわりがあります。その中で、私が参照している考え方としては、語る人が見ている状況や景色、取り巻いている状況を、その人の言葉のままに知ることが基本になるかと思います。
そうしたお話を聞くために、なるべくはじめのうちは質問や介入をしないことを心がけています。インタビューの形式になりすぎないようにするためには、背景や情報はある程度事前に頭に叩き込んでおくこと、かといってその情報をこちらが羅列しないこと、雰囲気を邪魔しないように座る位置を考えること、じっくりと話を聞くこと、自分の目線をコントロールすること、間を大切にすること、そして、ゆっくりと理解してもいいから安易に相槌しすぎないことを大事にしています。耳で聴いて、手でメモを取るというよりは、その人が生きてきた景色や感性、知覚、状況を身体で感じ取るという感じでしょうか。
9.「聞き書き」の心理的な効果についてお伺いします。「話す」ことを「誰かに聞いてもらう」ことにはどんな心理的な効果があるのでしょうか。また、何らかの効果があるとして、その効果が逆方向に働くこともあり得ますか?一方、「書き」は(「書かれた言葉を読むこと」は)、話者と聴者それぞれにとってどのような効果をもたらすのでしょうか?
本当はセラピーの要素もきっとありますが、なにせ私が臨床的な資格を持ち合わせていないため、効果について私から「こうだ」と言えることは多くありません。
ただ、専門職ではないにせよ、自分の持ち合わせた聴く力と、関係性を築き上げながらインタビューの中でたくさん質問を投げかけず、ただ実直にその人のお話に向き合うと、目の前にいる人が何をじっと見つめ、あぐみ、もだえているのか。そのリズムがあるときはぐっと重なり深まり、あるときは離れるような感覚がわくことがあります。
決して、話題自体やその人の合理性、この感覚の理由や原因を私が容易に理解できるわけではないし、はっきりと言葉にまとめられるわけでもありません。ただ、安易に解決志向に話を持っていかないにせよ、今ここで聞いている渦巻いている状況や話の中に巻き込まれ、ともに佇むという倫理的な態度は、聞き書きにとっては重要なモメントだと私は思います。
また、聞いたことを、なるべく聴者の解釈を多く入れずそのまま書くという聞き書きは、話者の言い淀みや繰り返し、話し方の癖や方言、冷笑や喜びの笑い、静けさの間などが可視化されるわけです。
それは、先ほどの特有の話の深度、懊悩、言葉にしづらい領域に対して、話者や聴者、そして読者すらともに巻き込まれ、とらわれながら内観的にその言葉や出来事自体について潜在的に知るという効果をもたらすことになるのかな、と思います。
10. 話者との信頼関係を築くために、特に気を配られていることはありますか?
いろんな人や背景、信頼関係の築き方があるので、一概に「これだ」と示すのは難しいですね。ただ、言葉づかいやバイアスにはすごく気をつけるし、怒られたり傷つけたりしたら、私の解釈ではどうこうと言い訳がましくごねず、きちんと謝ります。
しっかり自らが発する言葉を見つめないといけません。それが信頼関係を築く上で重要な態度かなと思います。
11. 今年2025年の目標を「会うこと、挑戦すること」と定められています。また、academistでの活動報告でも、災害・復興という、明るい見通しを持ちづらい研究テーマを言葉で進めることの「チャレンジ」について書かれています。今の土田さんにとっての最大の挑戦は何ですか?
誰に会うか、誰に伝えるか、誰に何をどうやって書くのか、という方法論的な理念をどう打ち立てるか、という挑戦ですね。会いたい人に会うこと、行きたい場所に行くこと、想いを馳せることすら、すごく躊躇って避けてしまったり、悩んだりする時期もありました。
まだまだ拭いきれないところもありますが、それらを時間をかけて乗り越えたことで、みなさんのおかげでたくさんのご縁や出会いがあり、心から「会うことはすごく大事なことだ」と改めて実感しました。今はできるだけ、みなさんや各地に会いたい、訪れたい。感謝の気持ちや「こんな風景や語りを見聞きして、研究として昇華し、今それを届けたい」という想いを胸に、いろいろ挑戦したいですね。

2024年8月 石川県珠洲市 外灘の海岸にて。前景には燦々と咲くひまわり、 後景には地震により隆起した白い岩礁(撮影:土田氏)
12. 今後の研究のご予定を、差支えのない範囲で教えてください
とてもシンプルで、まずは普段の生活や研究、教育、人との出会いを大事にしながら、まとまった時間を作って、できるかぎりフィールドに通うことですね。それに尽きます。その延長として、論文やエッセイ、記録と対話の時間が開かれるのかな、と考えています。
13. 文化人類学者である土田さんにとっては、各地のフィールドが研究所の役割を担うのかと拝察します。実際に東京、京都、大阪、石川、佐賀、宮崎、スリランカ、と精力的に移動・活動されていますが、各地を移動する研究者としての土田さんが、自分がもっとも帰属意識(Sense of belonging)をお持ちの場所はどこですか?
宮崎とスリランカは帰属意識が強いですね。空港に降り立ったとき、暑さや湿度、匂い、目や耳に入る文字や言葉、喧騒で「ああ、帰ってきた」って思える場所ですね。離れることが決まっちゃうと、本当に名残惜しい気持ちでいっぱいになり、いろんな人に「寂しい」と私がポツリと呟いちゃって。
そうすると、スリランカだと例えば「また帰ってきてね、というか来るよね?リオ(スリランカでの私の呼び名)の好きなご飯を用意して待っているよ」って返してくれます。最近取りかかっているスリランカでの宝石の調査で、お世話になっているホストブラザーの70歳過ぎのお母さんは、私の頭をゆっくりと愛おしそうに撫でながら、無事と徳を祈って仏教の言葉を唱えてくれます。そうした人の優しさや温もりを肌で感じると、余計立ち去りがたくなりますよね。
最近、佐賀にもそうやって遠くから私の存在や活動を見守ってくれる人たちのつながりを感じ、愛着がどんどん湧いてきました。たくさんお土産も持たされて、本当に嬉しかったですね。もっと石川もそんな感じで通っていけたら、愛着以上の愛おしさが湧くと思います。関西は、学びや住まい、仕事の場として根付いている感覚が強く、今ではありがたいことにいろんなつながりや友人が多いですね。
14. 地球温暖化を始めとする様々な環境問題が世界各地で災害を引き起こしています。研究成果を英語など日本語以外の言語で発信するご予定はありますか?
少しずつ、これまで考えてきたことや実践してきたことは、英語論文にまとめています。スリランカのことに関しては、ひとまずフィールドでお世話になった人たちに英語で成果を還元しましたが、調査で関わった人の中には高齢者や英語に慣れていない人たちもいます。いずれは、シンハラ語(スリランカでメジャーな言語の一つ)などでやさしい言葉や説明にまとめ、本人たちに伝えてみたいと思います。そして、その対話も大事にして、今後の研究の糧や導きの指針にできれば、この上ない喜びですね。
15. 海外の同じ学問領域・異なる学問領域の研究者との交流はありますか?もしあれば、どのようなツール、連絡手法でどのような対話をされていますか?
災害研究関連だと、WhatsAppやメーリングリストを通じて交流がたくさん行われています。これは結構日常的に情報が更新されていきますね。
その他、ここ最近、コロナ禍を経てまとまった研究資金を得たおかげで、やっと海外学会に対面でもハイブリッドでも参加しやすくなってきたので、実際にそこでの交流から気の合う研究仲間をちょっとずつ増やしています。頻度は多くないものの、メールで文通のようにやり取りしたり、オンラインビデオ会議などを通じて交信したりしています。
16. 土田さんの研究活動の原動力やインスピレーションは何ですか?
自分の原体験とその時に感じた不思議が原動力になっていますね。例えば、学部生の時は、とかくいろんなことに関心がありすぎて、指導教員も研究分野も定めるのが大変でした。迷走の最中で卒業研究のテーマを決めるとき、学んできたことと自分の気になっていたことを重ね合わせていたときにふと思い出したのが、大学進学時に老朽化した自宅をスクラップアンドビルドした出来事で、すごく印象的でした。自分が生きてきた時間や空間があっけなく壊されていく様子を見て、蓄積された記憶の沈澱を喚起し、家族とかつての家について共有することが多くなりました。そうした、今ある時間や空間を、人が災害や紛争、環境変動など何かしらの大きな変化を通して、どのように共有できるのか、実存として生き抜くのか、という大きな問いは、今思えばそれが原点のように思いますし、すごく大事にしたいなと思います。
インスピレーションは、専門外の本を読むことを通して得ることが多いです。本当に恥ずかしいことに、学部生から大学院生前半まで、本をじっくり読んでも言葉が抜けていった時期があって、概念・事象・理論の理解がなかなかできず、本を読みこなすことができなかったんですね。当時は私自身に対する失望も絶望もありました。今では古典から新しい議論に関する本や論文をあらゆる分野の先生たちから教えてもらい、ともに学ぶ機会がとても多いです。さらに、そうして得たものを実践やその観察を通じて、身体や感覚で考えたり、同僚たちと議論したりすることによって、概念などへの理解を深めています。ここ最近は、防災や復興の文脈に加えて、特にケアや自らの経験に関する記述の方法についての理解がより深まりました。

研究会エクスカーションで静岡県西伊豆町へ訪問。地元の議員や専門家を交えながら景観や住まいなどを観察して語ることで知の回路が開かれる(撮影:土田氏)
17. 研究で行き詰まりを感じる時の対処法は?
基本的に追い詰められて研究を進めるタイプです。集中の波とムラがたびたびあるので、行き詰まりを感じた時はあの手この手で一旦研究から離れて、短い時間で集中し、研究とは異なる頭や手、五感の使い方を研ぎ澄ませる時間を作ります。例えば、手を洗う、歯を磨く、好きな匂いのハンドクリームやバームクリームを塗る、ご飯を作る、シャワーを浴びる、アコギをつまびく、茶を点てて飲む、セラピー音楽を聴く、仮眠をとる、自転車を漕いでちょっとだけ遠出する、散歩する、お香を焚く、川辺やアパートの屋上に椅子を持って行ってぼーっとする、カフェに行く、などです。これといったルーティンは決まっておらず、気分で何をするか決めています。根詰めすぎて考えがちょっと煮詰まった際、別の作業を通して思考や作業のスケールをずらすことで、戻ってきた時により頭が冴える感じです。
そうはいっても、にっちもさっちも進まない、非常に重い思考が必要な時間や、やらなきゃいけない研究もあります。そうした中長期で詰まりそうな予感がしつつ余裕があるなら、思い切って別の原稿や資料を作ったり、関係がありそうでなさそうな本を読んだりします。あるときは目の前のことを放り出して、思いっきりキャンプしたり、できればサウナがあるか近くにあるホテルに泊まって缶詰作業に入ったりします。
結局、現実に戻ってきて悩み詰めちゃって、締め切りギリギリでえいやって出すことが多いです。悪い癖ですね。いつも出し終わってから反省します。
18. 日本の学術研究を発展させていく上で、研究者たちにとって望ましい環境とは?
あらゆる人と出会い、対話するための時間と環境だと思います。もちろん、目の前のことや研究に集中して取り掛かる時間や、自分や身の回りの人たちと生活する時間も大切です。それはきっとどの人も共通して伝えることでしょうから、その上で、どう時間を過ごすことができるのかと考えたとき、気軽に、ときには真剣に話をしに行く同僚や先輩・同期・後輩、海外の仲間、さらには業界や業種も超えるかかわりあいをもって、ゆるくてもバチバチにでも話せる時間と場が意図的でも非意図的にでも必要なのかなと思います。やっぱり出会うことが大事ですね。
19. 最後に、博士課程に進もうか迷っている修士・学部生にアドバイスをお願いします
国内外問わず、憧れている先生や論文、本、そして魅力的な現場・人・研究室に出会い、まずはそれらを大事にしてください。そして、できるならその先生たちに会って、憧れていること、今考えていること、悩んでいることをぜひ率直に伝えてみてください。きっと自ずと行きたい道や場所が開かれると思います。
クラウドファンディングサイト「academist」の土田さんのページはこちら。クラウドファンディングに挑戦する理由や現在取り組まれている研究課題についてお話しされています:
https://academist-cf.com/fanclubs/361
こんな記事もどうぞ
櫃割仁平氏へのインタビューー「美は世界を救う」を心理学で実証したい
渡部 綾一氏へのインタビューー意識の発達の多様性を解明し、子どもたちが生きやすい社会を目指す!