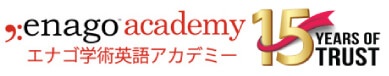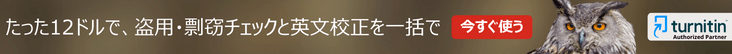比較文学とは何か

比較文学とは
比較文学(Comparative Literature)とは、異なる文化圏や言語圏の文学作品を比較し、その相違点や共通点、相互作用の過程を探る学問領域です。
国や文化、言語の時代の枠を超えて文学作品を比較し、そこに共通するテーマや手法、影響関係を明らかにしようとするこの試みは1800年代のフランス等でもその萌芽がみられ1、20世紀初頭にフランスを皮切りに大きく発展したとされます。(フランスで、フェルナン・バルダンスペルジェFernand Baldenspergerがポル・アザールPaul Hazardとともにこの分野の最初の学術誌 『Revue de littérature comparée』を発刊したのが1921年、前ロマン主義文学pre-Romantic literatureを研究したバン・ティーゲムPaul Van Tieghemがソルボンヌで「比較文学」を講じたのもほぼ同時期のことでした2。)
そして、この1世紀あまりの間に、多くの国や地域で比較文学研究が行われるようになり、「比較文学研究」に分類される学問領域のテーマや対象、研究手法は多様化しています。特に異なる文化や言語の文学を比較するには、多くの場合、作品どうしの比較だけでなく、文学作品のテクスト、他の芸術様式や社会・歴史・政治的な背景との関りから考察することが避けられないでしょう。
このことからしても、比較文学という研究分野自体が一定程度以上の学際性を内包し、研究の幅に広がりが生まれてきたことも自然な流れであったと考えられます。
テーマ、対象、方法
上述のとおり、比較文学の研究方法は多岐に渡りますが、主なアプローチには以下のようなものがあります。
- 影響研究:: ある作品(群)が他の作品(群)に与えた影響についての研究。特定の作家間の直接的な影響関係を調べたり、作風や構造、様式の伝播を探ったりします。
- テーマ研究: 異なる文化圏における同一テーマの描かれ方を比較する研究。例えば、「死」や「愛」、「自由」などの普遍的テーマが、異なる文化圏の作品においてどう表現されているかを研究します。
- 類型研究: 異なる作品(群)に共通する類型やモチーフを浮かび上がらせる研究。例えば、異なる文化圏の神話や伝承に共通するモチーフの比較による、人類にとっての普遍的な物語の探究などです3。
- 受容史研究: ある作品が異なる文化圏でどのように受容され、解釈されてきたかについての研究。例えば、日本の古典文学が海外でどのように翻訳・翻案されてきたか。「翻訳」の果たす役割についての研究も重要なテーマです。
- 文学と他の芸術形式の相互作用:映画や音楽、絵画など、他の表現との関係性の研究。例えば、文学作品の映画化についての研究や、物語の中で描写される音楽・絵画・演劇などに関する分析です。
- ジャンル比較:異なる文学伝統におけるジャンル(詩、小説、戯曲など)の発展や、変容を比較する研究。それぞれの形式の文化横断的な特徴や差異を探ったり、同じ文化圏でジャンルの持つ特性を明らかにしたりすることは、学術以外のフィールドを含め多くの人の刺激になるでしょう。
個々の研究においては、これらの研究方法のうち、単一の方法が採択されるとは限らず、研究対象や目的により、複合的な手法が用いられます。
手法の多様化・多様な視点
比較文学という学問領域では、直接的な成果として異文化理解の増進などが期待されるものの、ヨーロッパにおいて誕生した当初の研究には西欧中心、男性中心的な視点への偏りが指摘されます。
しかし20世紀を通じて各国で西欧中心の文学史観からの脱却が行われ4、より多様な視野が研究にもたらされるようになりました。20世紀末から今世紀に注目されてきた比較文学研究者の中で、エドワード・サイード(パレスチナ系アメリカ人)や、ガヤトリ・スピヴァク(インド出身女性)といった多様な出自を持つ人々が、ポストコロニアル的な視座をテクスト分析や批評にもたらしたことは示唆的です。
比較文学研究の意義
おそらく、人文科学系のほとんどの学問研究と同様、比較文学研究が実社会や世界の問題に対して即効性のある解決策をもたらすことはあまりないでしょう。しかし、混迷を極める現代にあって、多角的な視点でテクストや世界を分析すること、そしてそのことによる想像力の涵養に、期待すべき事がないはずもありません。
参考
『比較文学比較文化ハンドブック』(東京大学出版会、2024 年)
東大比較文學會のサイトでは多くの研究書誌がリストアップされています。
http://www.todai-hikaku.org/bibliography/index.html
注
1 例えば、19世紀フランスの歴史家・著述家ジャン=ジャック・アンペール(Jean-Jacques Ampère)は、1830年代に「諸民族の芸術と文学の比較史(histoire comparative)」を研究し、De la littérature française dans ses rapports avec les littératures étrangères au Moyen Âge(『諸外国文学との関係における 中世のフランス文学について』と題する書籍を刊行。
3 例えば、中沢新一先生が講義録を元に上梓された「カイエ・ソバージュ」シリーズの第1巻『人類最古の哲学〔新装版〕』(講談社、2023年)では、異界とつながる「灰」や「かまど」の傍に身を置くシンデレラの物語が、ユーラシア大陸全土に残されるいくつもの異文(バリエーション)とともに紹介されます。