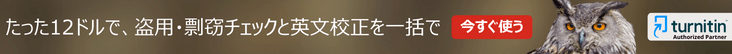博士号取得のための歩みを止めていませんか?

オーストラリア国立大学のインガー・ミューバーン教授のコラム「研究室の荒波にもまれて(THE THESIS WHISPERER)」。今回は、意識的・無意識的に論文の提出を遅らせてしまう博士課程の学生についてのコラムです。
先日、オフィスの前のバルコニーで、ANUの後期博士課程の学生2人と素敵なランチをしました。ANUのクィディッチ*チームが目の前の楕円のフィールドではしゃいでいる間、私たちは冬の終わりの日差しとブラック・マウンテン・タワーの眺めを楽しみました。アカデミアが楽園のように思える瞬間でした。広大な公園の真ん中で、興味深いことをしている頭のいい人たちに囲まれて、しかも嘲笑されることなく箒を股に挟んで走り回れるような場所で仕事ができるなんて、他にあるでしょうか。
*クィディッチ(Quidditch)はハリーポッター・シリーズで登場する箒に乗って行われる魔法界のスポーツ。
私が、ANUの美しいキャンパスは博士課程の学生であることの特典のひとつに違いないと言うと、食事を共していた学生たちも同意しました。ひとりは、博士課程をできるだけ長く引き延ばしたいと思うのは当然だとしました。終わればすぐに大人の責任が押し寄せてくるから、というのです。
こんな暮らしは、資本主義世界から遥か遠くの離れた世界である一方で、資本主義世界の多くの利点を享受することもできるものです。ですから、博士課程での研究を遅らせる人々の50%ぐらいは、この素敵なライフスタイルを享受するため、そうしているのに違いないと考えたくなります。しかし、現実にはもちろん、このような状況にあるほとんどの人は、博士号という重荷を取り除こうと必死なのです。大人になってから貧困ライン以下で生活するのは楽しくありません。研究は社会生活に食い込んできかねないですし、実際に食い込んできます。たいていの研究プロジェクトは3年ぐらいで少なくともある程度は退屈になってきます。
しかし、博士課程の学生としての生活が成り立たなくなってきていても、論文提出に後ろ向きでいる不可解な人々がいます。お金が底をつき、人間関係がぎくしゃくしているにもかかわらず「身動きが取れず」、提出に必要なステップを踏むことができない(あるいは踏み出そうとしない)のです。
そのような人に会ったことがある方もおられるでしょう。いつも、あと1章書かなければならないとか、さらなる文献レビューが必要だとかするのです。小うるさい指導教官のせいでそうなる場合もありますが、指導教官という人々の中では完璧主義者よりも絶対的な現実主義者の方が圧倒的に多いため、一般に思われるほどそうしたケースは多くはないでしょう。
不幸な一部の学生は、自分の研究が博士号の水準に達する見込みが薄いにもかかわらず、あきらめ時を認めようとしません。私の知人には、すべてが崩壊していく中で、決断を下すことを拒み、宙ぶらりんの状態で生きている人もいます。それを見ているのは辛く、苛立たしいのですが、黙って彼ら自身に解決を任せるのが最善だということを、私は身を持って学びました。彼らを批判したり、彼らが従えない(あるいは従いたくない)アドバイスをしたりしても、何の解決にもならないのです。
さっさと提出するか辞めてしまうのが合理的で理にかなった行動という状況で、しつこく続けようとする人がいるのはなぜでしょう。理由は複雑ですが、厄介なアイデンティティの問題が絡んでいるケースもあると思います。意識的あるいは潜在意識的レベルで、「博士課程の学生」という肩書がなければ自分はどうなってしまうのだろう、と心配するのです。そのアイデンティティを手放すという決断は、特にそれに代わるものがすぐに見つからない場合、深刻なアイデンティティ喪失の危機をもたらす可能性があるのです。惰性で残っている学生を責めるのは早計です。
今は亡き偉大なアリソン・リー教授(Alison Lee)は、この分野において、自身の最高の研究成果を成し遂げ、研究教育についての研究者たちが、博士課程のコミュニティにおけるアイデンティティとアイデンティティ・ワークの役割に目を向けるきっかけを作りました。私の友人であるメアリー=ヘレン・ウォード博士(Dr. Mary-Helen Ward)は、博士課程学生の教育についての論文を書いており、この分野の包括的な文献レビューが含まれているので、興味のある方は参照してください。仕事に取りつかれた私たち西洋社会においては、アイデンティティの意識は仕事と密接に結びついているため、こうしたアイデンティティの問題は私たちの多くにとって非常に現実的で、悩みの種となっているのです。
クリスティン・ソレル・ディンキンズ(Christine Sorrell Dinkins)とジャンヌ・マークル・ソレル(Jeanne Merkle Sorrell)による“Our Dissertations, ourselves(『私たちの論文、私たち自身』)という新刊は、アイデンティティの問題に関して興味深い視点を提示しています。ナンシー・フライデー(Nancy Friday)の名著『My mother / myself』(『母と娘の関係―「母」の中のわたし、「わたし」の中の母』)を引いているタイトルからも、この本は女性の経験に焦点を当てているのだろうと思いましたが、その通りでした。
著者たちは、論文完成までの旅路について多くの女性にインタビューし、執筆、孤独、人間関係、指導など、学生の主要な問題を反映する章立てにしています。インポスター症候群についての論考は、これまで見た中で最も優れたもののひとつです。各章の最後が、同書で最も有用で実践的な部分だと思います。人生で起きている問題を探り、それに対してできることを考え上で役立つ一連の質問です。
全体として有用で興味深い本ですが、この本の潜在的な読者にそれほど興味を持ってもらえるかについては心配です。ほとんどの学生は、何の助けも借りずに私生活や博士論文の悩みを解決するぐらい満ち足りているようなのです。物語をナビゲーションとして使うことに興味がある人は、このブログや、私がリンクしている多くの博士課程の学生のブログで、たくさんの実例を無料でお読みいただけます。
“Our Dissertations, ourselves(『私たちの論文、私たち自身』)のストーリーの分析はかなり理論的な傾向があり、人文科学のバックグラウンドがない読者には敬遠されるかもしれません。また、女性の経験に重点を置いているため、男性には敬遠されるかもしれません。もし私たちの数字が確かなら、退学率が高い男性の方がこの種の本をより必要としているのかもしれません(出版社さんへ:男性に焦点を当てた続編をぜひお願いします)。
もうひとつのターゲット読者は指導教官で、すでに指導教官を務めている人、あるいはもうすぐ指導教官になる人には、ぜひこの本を手にして読んでもらいたいです。学生指導の問題のひとつは、私たちが実践の基礎とする学生のサンプル数が限られていることです。このような本は、指導の実践を豊かにするケーススタディをたくさん提供してくれます。しかし、やはりほとんどの指導教官は、何の助けもなく、また自分自身の実践を振り返ることもなく指導を続けているようです。少なくとも何人かがこの本に出会い、学生たちがその恩恵を受けることを願います。
あなたはどう思いますか?痛々しいほどに論文提出を遅らせている人に会ったことがありますか?無意識的、意識的に、この先どうなるかを心配して、タイムリーな論文完成を自ら妨げる方法を見つけていないでしょうか?他の人の成功談は参考になりますか?ぜひお考えを聞かせてください。