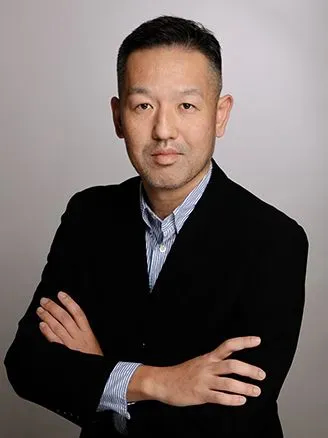
石岡 丈昇(いしおか とものり) 教授
日本大学文理学部社会学科 教授
石岡丈昇先生へのインタビュー - Share Your Story
[取材・編集] 研究支援エナゴ
長期間にわたり対象世界で過ごして人びとの生活について記述する「エスノグラフィ」で社会学の研究を行う石岡丈昇先生。フィリピン・マニラのボクシングジムでのボクサーたちとの生活を元に上梓された『ローカルボクサーと貧困世界』1や『タイミングの社会学』2は、研究者だけでない多くの読者を獲得しました。
2025年5月に行った今回のインタビューでは、これまでの研究で用いてこられた定性的な手法、身体性・貧困といったテーマを扱われてきた背景などのほか、広く人文社会科学的な実践や、書籍との関わり方、海外での学会発表やネットワーク作りの大切さなどについてお話しいただきました。
「彼らの世界」を研究するのが文化人類学だとすると、社会学は「我々の社会」を研究する学問だといいます。内的・個人的なモチベーションのある研究にこそ持続性があるという石岡先生が、他者の経験を集めて記述しながら、社会を捉えられているということが印象的でした。
社会学/身体文化論に興味を持ったきっかけ
社会学を勉強したいと思ったのは大学に入ってからです。それまで何をやりたいか明確に考えていたわけではなく、色々な授業や講義を聞く中で、社会学や社会学的な発想に強く興味を持ちました。私自身は本を読んだり抽象的に思考したりすることも好きなのですが、フィールドワークという形で人に会って話を聞きながら、純粋に学術的な動機で物を調べ、書き、発表するという研究者たちの姿に感銘を受けました。これが、大学という場で行われている研究なのだ、と。そうした先輩研究者たちの姿を見て、自分も社会学を研究しようと思い大学院に進学したのが研究者としての第一歩です。
ご自身の研究への向き合いかた
「問う」ということの面白さ、自分で問題設定をして調べることの面白さに目覚たのは、先輩研究者たちの影響によるものですが、大学の社会的責任というものを教わったのも大学院に入ってからです。
私はフィリピン・マニラの貧しい地域に暮らす人々の生活について調べるフィールドワークをしていますが、私の行う学術的な研究が、これまで表出してこなかった声や生活の中身を文字にして、日本語だけでなく英語で人々に伝えるのはとても重要な営みだと考えています。
しかし一方で、フィールドワークや社会学的・文化人類学的調査が、支配のために使われてきたという歴史もあります。相手の生活を知ると支配が容易になるため、学術的な関心や知識を生む大学が植民地支配に密接に絡んできたのです。私は、学術の持つ可能性と同時に、学術の「巻き込まれ方」についても繊細に考えるようになりました。今でも、いかにして、学術のそうした側面から批判的に距離を取りつつ、人々の声を発信すべきかを考えながら研究を続けています。

生活を共にしながら行う調査
社会学には大きく2つの研究手法があります。1つ目は数量化して示す量的研究です。例えば「貧困」が研究対象であれば、収入がいくらで支出がいくら、そのうち必要な食費はいくらというように、対象を数字として把握していく手法で、これはこれで重要です。
私は、数字を使った調査も行ってはいますが、人々の実感や「声」といったものを捉える質的研究の手法を採っています。例えば台風が起きた時の経験は数字だけでは示せず、恐怖や、家族が見つからない不安などといった数字に表せないものを書き記していきます。そして、そのようにして集めたマニラの人々の台風の経験を英語論文として発信すると、チリでフィールドワークを行う研究者と「貧困地区と災害」という視点で議論が発展することもあります。「声」を拾う質的研究のアプローチは、普遍的な人間の実存を捉える研究手法としてやりがいがあります。
社会学と文化人類学の違い
正しいかどうか議論のあるところですが、文化人類学が「彼らの世界」の研究であるのに対し社会学は「我々の社会」の研究である、と言われることがあります。
例えば、イギリスの研究者が植民地であったインドやメラネシアに行き、そこで暮らす人々の、西洋近代とは異なる生活習慣などを細かく調べ、人間とは何かのトータルな把握を目指す。そのように発展したのが文化人類学です。イギリスの研究者にとっての「自分たちの社会」ではなく「彼ら/彼女らの世界」を研究するのです。
一方の社会学は、基本的には「我々の社会」を研究します。例えば日本の社会学者であれば、日本の東京で様々な産業問題の研究をしたりする。文化人類学の場合、遠く離れたものとの対話で人間理解を深めるという特徴があるとされますが、社会学の場合は、まさに自分が生きている世界を考えていくという発想で研究を行います。私の場合は、産業都市に関心がありましたので、遠く離れてはいるものの大都市であるマニラの生活を研究してきました。
シカゴ学派が確立したエスノグラフィ
フィールドワークによって人々の行動を観察し記録するエスノグラフィの手法を盛んにしたのは、アメリカ・シカゴ大学のシカゴ学派と呼ばれる研究者たちです。当時のシカゴは産業が急速に発展し、多様な人々が流入しました。移民同士の争いが絶えなくなり、街の秩序の維持が難しくなった時に、そもそも街がどういう状態なのかをエスノグラフィの手法で調査し、調査結果を都市政策に活かそうとしたのです。こうして、「彼ら/彼女らの世界」を調べてきた文化人類学の手法が、「我々の社会」を研究する社会学にも導入されました。そうした流れの中で私も自分の研究を組み立ててきました。
先行研究などの書籍・文献を詳細に解説する意図
私が自分の著作の中で、国内外の関連研究を丁寧に紹介する理由は2つあります。1つ目の理由は、多くの日本人の社会学研究者が、論点だけを書いてしまい、論点にたどり着くまでの関連研究の紹介を苦手としている、と考えているからです。
例えば「この研究は、この論点が新しく、これが新しい概念だ」という説明は10秒ぐらいでできます。しかし、この10年程外国人研究者たちと議論する中で、それではダメだと強く実感するようになりました。主要な論点だけでなく、そこに辿りつくまでの流れも大切なのです。具体例を使い、読み手と書き手の間に共通のイメージを作る。論点をストーリーとして語る。ストーリーテラーである自分には論点はよく理解できていますが、読み手には理解できていないことが多いのです。
辞書の一項目のように論点だけを暗記しても、次に派生していきません。派生させるためには、ストーリーやプロットの中に論点を入れなければならないと海外の学会などで学んだのです。20分話す時間があったとしても、話すべきポイントは一点だけでいいのです。たとえ時間が60分あっても一点でいい。その一点に向かって話を準備していき、そして、その一点の論点に到達した次に何が見えてくるのかを想像させながら話すのです。

しかし、詰め込み型の受験勉強を経た日本の研究者は、一つの話に複数の論点を盛り込んでしまい、聞き手に結局何が一番のポイントなのか理解されないということがよくあります。
ですから、私は、英語でも日本語でも、自分が読んで面白いと思った文献を紹介する時には、その文献のポイントをできるだけ丁寧なストーリーの中で論点を入れ込みながら紹介しています。このやり方を考えるようになったのは、研究の文脈や背景を共有しない外国の研究者たちと会話をするためには、一つずつ、丁寧に説き起こしていかなければならないと気づいたためです。
2つ目の理由は、一つのものから複数の視野を広げていくという手法に魅力を感じているからです。例えば授業でも、私は文字を書き込んだパワーポイントを使いません。文字が書かれたパワーポイントを使う教員の方が多いとは思いますが、重要なのは文字を追うことではなく、絵やイメージからどのような論点を喚起していくかです。90分の授業用スライドでもせいぜい10枚程度のイメージしか使わず、それらがどのように広げられるかを示していきます。一つのものから、様々な派生や展開が生まれることに大きな魅力を感じているために、このようなやり方になってきたのだと思います。
研究者が学術誌以外の一般書籍などで情報発信する意義
文系の研究者と理系の研究者では少し事情が異なると思います。物理や生命科学などの分野では、科学の発展に貢献するという意味で、論文の執筆と学術雑誌への発表が最も重要になるでしょう。
一方、人文系の場合、日本だけに限らず、一般書という形での書籍の出版が重視されています。人文科学の場合、新しい考え方や価値観を生み出すことが使命でもあるため、学術誌に書くだけでなく、一般書籍の執筆と出版によって大学を超えた人々に成果を届けることの意義が大きいのです。特に、平易な文章で新書などのフォーマットで本を出すと、高校生や、働きながらも学ぶことに関心を持ち続けている人々にもメッセージが届けられます。そのような観点で、最近の私は本を書いています。
エスノグラフィの文献・書籍は、読み手に何をもたらすのか
読んだ人が、そこに自分の姿を発見することがあるのだと思います。フィリピンのマニラでも、ケニアのナイロビでも、日本の東京でもいいのですが、そこで起きていることが読み手の世界とはかけ離れた大変なことだという書き方のルポもありますが、エスノグラフィが目指すのは必ずしもそこではありません。
私が目指すのは、一見離れた世界の中で人々が陥っていることがよく分かり、そこに自分の姿を発見できるようなエスノグラフィです。遠くのものに近さを感じたり、逆に近くで当たり前に感じていることが、実は外に出てみたら全然普通のことはなく、私たちが普段やっていることの方が特殊かもしれないと感じたりするというように、遠近法的な視点を与えられるエスノグラフィが学術的には重要だと考えてます。
結局、人文社会科学とは、知識とか認識を生み出し豊かにするための学問領域だと思うのです。凝り固まった図式のままデータだけを集めても新しい発想やアイデアは出てきませんが、一見遠くのものに自分と同じものを発見したり、そのことを通じて自分たちが身近で絶対的な真実だと思っているものが他でもありえるという風に揺さぶられたりするところから、新しいアイデアや着想や認識の枠組みは作り出されていく。それがエスノグラフィのポイントだと考えています。
人文社会科学が目指すところは何か
触れたことのない考え方やものの見方に触れていき、それに沿ってデータを整理してみると、ある問題の別の側面が分かって来ることがあります。例えば貧困を考える際、お金の少なさゆえの日々の生活の困窮という側面も大切ですが、貧困を時間の問題として考えてみることもできます。常に財布の中のお金が少なく、頭の中がそのことで占拠され、先のことを考えるのが難しくなってしまうというように、貧困の問題を、金銭をどれだけ持っているかだけでなく、時間の経験への影響という観点から考えることもできるのです。
視座や認識を変えることが、貧困問題への新しいアプローチを作り出し、貧困問題を捉える枠組みを柔軟にさせていくことにも寄与すると思います。そしてそのような知識や認識の生産が社会科学にとってはとても重要だと思います。

フィールドワークにおいて心がけていること
すぐに話を聞こうとしないこと、でしょうか。
まず、そこでどのように人が動いてるのかに身を寄り沿わせることを私は重視しています。私が尊敬する文化人類学の先生がよく「フィールドワークで一番大切なのは、調べる前に、そこでまず普通に生活ができるようになることだ」と言われていました。もちろんフィールドワーカーはアウトサイダーであり続けるのですが、それでも、来てすぐに質問をして帰っていくよりは、まず、自分でも現地の人と同じように、食べて、寝て、掃除をして、洗濯をして、そこでの生活がどういうことなのかを体感することが大切です。質問や調査は、その後に進めていくべきだという教えを私は大切にしています。
指導する学生にもよく話すのが、マニラにいた時の洗濯場での体験です。現地では、洗濯は手洗いで行うため、私にとっては本当に辛い時間でした。しかし、暑い中で汗を搔きながら時間を掛けて作業している私の下手さ加減を見かねた人に「こうやるんだ」と話しかけられて、そうするうちに話を聞けるようになったということがありました。やはり何かをしながら話を聞くというのは大切なことだと思います。生活の場だからこそ聞けることもあるのです。
現場と研究室を往復しながら、問いを鍛え上げる
量的研究の場合、事前に研究デザインを練り上げた状態で現地に行かなければ、1万のサンプルを取ってもひどい結果になってしまうかもしれません。しかし、私のように質的なフィールドワークを行っている研究者は、むしろ現地との往復を重ねながら問い自体を練り上げていくという側面が強いです。
例えば「貧困」などといった大枠のテーマを携えて現場に行き、そこで取材や調査をさせてもらいます。そして戻ってきてからデータの整理や先行文献の読み込みを通じて次のフィールドワークで聞くべきポイントをブラッシュアップしていく。予め問いを立ててから現場に行くというのではなく、現場と研究室を往復しながら問いを鍛え上げていくというのが私たちのやり方です。
今取り組んでいるプロジェクトでは、アスベストや汚れた空気の中での長期の労働によって肺を痛めてしまった人々について、実際に取材したり、記録などを読んだりしています。人間と世界の境界といえば皮膚を思い浮かべますが、皮膚だけでなく肺も境界で、呼吸においては中継点です。マニラなどの排気ガスを吸えばその境界・中継点としての肺は傷んでいきますが、病に罹患しダメージを受ける度合いは、社会の階級やジェンダーなどの社会的な変数に影響を受けます。それについて研究しようとしているのですが、これも明確なリサーチクエスチョンが先にあったわけでなく、境界・中継点としての肺という観点から取材していくうちに、人工呼吸器を付ける人々のストーリーや、彼らが機械とどう接続しているのかなどといった事例が緩やかに集まってきているのです。最終的に本や論文を書く時にはもっと明確な問いやテーマを立てるのですが、少し緩く集めていきながら問いを鍛えていくという作業を、今まさに行っているところです。
取材と執筆の時差がもたらすもの
物事を理解しようとするには、やはり一旦離れる必要があると私は考える方です。フィールドワーカーでも、家から通える範囲のところで1日の様子を取材して、また2日後にやって来るといった形の調査をされる人と、私のように一定のまとまった期間に調査に行ってまた戻って来るという人ではやり方も異なります。私の場合はしばらくの間現地に入って、しばらくの間戻ってくるという往復での研究で、そこで起きたことを書くため現地でフィールドノートは取るけれど、まとめるのは、そこから離れた違う場所です。そうして時差が生まれます。調べる時間と、記録や写真を整理して考える時間の間に時差があるからこそ、思考が深まっていきます。
整理するといえば、外国の学会で喋るのはとても良い機会です。自分が調べてきたことのポイントを端的に示さないと、外国の人たちは話に付き合ってくれません。全体が30分の発表であっても、議論のポイントを最初に打ち出して、それが学術的にいかに重要かを伝えなければいけない。研究発表を申し込んだ時点で、調査データをその場に向けてまとめ上げていくことになります。それにより、結果的に思考が整理されていきます。
調査を行い、フィールドノートを整理し論点を書き出して、研究会などでの発表で様々なコメントやフィードバックをもらって、もう一度フィールドに戻る、といった流れです。ですから私は、調査地と研究室と、発表の場を持って最終的に論文や本を書き上げていきます。発展途上のアイデアをアウトプットするために、私は国際学会を使ってきましたし、知り合いの外国の研究者たちもそういう風に学会を使ってる人が多いように思います。
フィールドワークの地で「常に飛び跳ねている」
去年、美学研究で著名な方と一緒にマニラに行きました。その人が日本で知っていた私のイメージと現地での様子があまりにも違ったらしく、すごくはしゃいでいるような私を見て、「フィリピンではいつも踊っているみたいな感じ。また次もフィリピンバージョンの石岡さんと会いたい」と話をしていました。これはおそらくフィールドワークをやっている人にはよくある話で、アフリカを研究フィールドにしている人の間では「アフリカの毒」という言葉があります。アフリカでの調査から日本に帰ってきても、すぐにまた恋しくなってアフリカに行きたくなる、といった中毒性のようなものを「アフリカの毒」と表現するそうなのですが、そのような「調査地の毒」があって、つい興奮してしまうということなのだと思います。私自身は至って普通のつもりなのですが。
あと、現地に行くとみんなよくジョークを言うので、それと同じモードになって違う顔が出ることもあるでしょう。
個人的な経験は、研究に関わるのか
社会学の研究の潮流の一つにフェミニズムがありますが、その標語に「個人的なことは政治的なこと3」というものがあります。昔の発想では、社会学は公共的な仕組みや機能を調べる学問で、個人的なことを持ち込んではならず、例えば都市の環境問題なら、それをどのように改善すべきかを考えるものだということになっていました。
しかし、公園がなくなったり、大気が汚染されたり、都市の環境の変化に影響されるそれぞれの人は、子育てや介護など個人的な課題を持って日々を生きているわけです。フェミニズム的な発想では、そうした個人的なことを括弧にくくって、それ以外の公共的なことを調べるということにはなりません。子育てや介護、あるいは週末に誰かと会うといったプライベートな経験こそが、パブリックで社会的な経験とつながると考えるわけです。
このように、現在では、個人的なことが社会学的な問題として扱われるようになっており、そのような流れの中で、私も生い立ちや育ってきた風土、環境を意識しながら自分の研究テーマを練り上げていくことを目指しています。
内的な動機がある研究の方が長続きすると思います。あまり関心を持っていない内容について、このテーマで書けと言われたとして、たとえ勉強して書けるにしても、それを書くことの内なるエネルギーは湧いてこない。歴史家にしても、社会学者にしても、哲学者にしても、内なるエネルギーが湧いてくるテーマと湧いてこないテーマがあると思いますが、自分にとって内なるエネルギーが湧いてくるものが何で、なぜそれをやりたいのかを絶えず意識しておくことが研究者として走り続ける上で必要だと考えています。
肉体労働をしていた父は生前、私の仕事について「クーラーの効いた部屋で、声だけでお金をもらう」などと言っていました。20世紀に生きた人々にとっては、今のように空調設備などがない中で働くのが当たり前で、「働くこと」イコール「汗を流すこと」でした。子どもにお小遣いを与える際に、その価値を、親が「汗水流して稼いだ」という表現で説明するほど、文字通り人は汗水を流して働いていたのです。

今、東京ではそうした労働は少なくなってきたと思いますが、世界的に見ると汗水流して働く人は山のようにいます。私は、そのような人々が生活の糧を得ながら、仲間を作り、楽しみを共有するという、体を使って働くことのリアリティに関心を持ってきました。そして、その象徴的な存在がボクサーです。社会学では、近代産業都市を可能にしているのは、体を使って働く人々が生み出され続けているからだとされますが、私は、ボクサーに限らず体を使って働く人々のことをこれまでも研究してきましたし、これからも考えていくと思います。
英語での発表の機会をどう活かすか
博士論文を書き、それを最初の単著として出したのが2012年です。その後は国際的なところで発表していきたいと思い、2013年から国際学会などに積極的にエントリーして研究発表してきましたが、苦労だらけです。
院生などに伝えたいのは、どこかに学術論文がアクセプトされて学術雑誌に載るか載らないかという段階に行く前に、まずは国際的な研究の友達を作ることが大切だということです。学会や研究会の目的には、発表だけなく、ネットワーク作りもあります。発表をして、それが終わればすぐに観光に行ってしまう院生も中にはいて、確かに発表はすごく緊張するし、準備にも時間がかかるためその気持ちは理解できますが、しかし他の人の発表を聞いて質問をして、コミュニケーションを取っていくということがやはり重要なのです。
最初は質問すること自体がすごく難しいでしょう。日本語で質問するのでさえ難しいのに、英語で質問をするのはなおさらですから、私としては大きな学会よりも、小規模のプロジェクトベースの研究会などをお勧めします。論文がアクセプトされるかどうかという段階の手前では、そこに足を運び、質問をしながら自分を認知してもらっていくというネットワーク作りを行うとよいでしょう。
その時大切なのは、自分の研究テーマと、自分がやっている研究の面白さを端的に話せるということです。それは英語が上手かどうかとは別の技能で、英語が上手でも要領を得ない話をしていれば相手にされません。たとえ英語が上手でなくても、ポイントを話し、今の発表と何がどうリンクするのかなどを、ゆっくりとでも伝えるのです。相手が求めているのは英語力ではく社会学の研究なのですから。
社会学の研究者として日本から来た自分のパースペクティブではこのように見えるといったコメントをすると、じゃあコーヒーでも飲みながら少し議論しよう、となることもあります。そして後日、別の学会で会えるならまた議論しよう、といったメールのやり取りができるようになるでしょう。実質的に会話をする能力の方が、論文自体を載せる載せないよりも実は重要かもしれないと思います。
学術英語についてのアドバイス
当たり前ですが英語を書くためには英語を読まなければいけないということです。日本にいて日本語しか使わない頭の構造の中で英語を書いて、それを英文校正に出しても多分上手く行かないと思います。英語で書くのであれば英語を読んで、頭そのものをその期間、少なくとも研究に関しては英語用のギアにシフトしてから書くことが必要だと思います。エスノグラフィを書くためにはエスノグラフィを読む必要があるように、英語で書くためには英語を読む必要があるでしょう。
面接を受ける人が、途中までは日本語話者、途中からは英語話者になるという面接の場に、面接官の1人として参加したことがあります。面接官側は日本語話者が2人か3人で、英語話者が2人でした。その日は、英語での面接に切り替わる前に少し休憩を入れ、近況などについての雑談を英語で2、3分してから、英語での面接を始めました。言語の切り替えが難しい場合は、こうした切り替えの準備をすることによって英語で話すことが可能になると思います。
学生時代に国際的な環境で学ぶ利点
学生時代や若手研究者の間に外国で学ぶというのは、自分から離れるために必要だと思います。異なる言葉での生活では、苦労もありますが、自分が日本語で話しているうちには気づかなかった課題の設定の仕方やニュアンスの違いも痛感させられます。日本語で育った人間が日本語の中にいると、つい自分にとって自明なものを持ったまま研究をしてしまうものですが、外国語の場に出て行けば、自明なものを一旦手放さなければ生活も研究もできません。
例えば、英語の「understand」は日本語で「理解する」と訳されますが、これは「under」と「立つ=stand」という語で構成されています。ドイツ語でこれにあたる「verstehen」にも「stehen=立つ」が含まれます。「理解すること」と「立つこと」が繋がるのは興味深いのですが、複数言語の状況に身を置くことによって初めて、そうした言葉の新たな捕まえ方をできるようになると思います。
ですから、外国語を勉強するというのは決して英語の点数を上げるだけではなく、それまで問わずに来た深い前提にまで立ち返って言葉をもう一度自分のものにするための行為でもあるのです。そして、そのためには外の環境に身を置き、自分から離れる必要がある。ですから自分から離れるために外国語を勉強し、外国語で研究することを私は勧めます。
海外の研究者たちとネットワークを作るには
日本語で本を書いていれば、日本国内ではある程度仕事内容を知ってもらえます。しかし、例えばチリや南アフリカ、ドイツ、フランスなど、海外の研究者たちは基本的に私のことを知りません。
互いのことを知らない時に最初の一歩として有効なのは、名刺代わりに論文を送り合うという方法です。学会などで、よほど相手の研究に興味を持って連絡を取りたいという場合は名刺を交換しますが、日本のように会ってすぐに名刺を交換することはありません。発表の隙間時間でたまたま会った人と話したり、発表を聞いて面白かった研究者と雑談をしてコメントを交換し合ったりして、その次にそれぞれ自分の研究を紹介するためにPDFで論文を送り合うという文化です。その時に日本語の論文しかないと相手は読めませんし、英語の論文でも、数年以内に発表した論文を送れる状態でいることが大切です。話すだけではなく書いたものがあることがやはり重要なのです。
しかし一方で、書いたものがあるだけでなく、その場でコミュニケーションを取れるというスキルも必要です。コミュニケーションを取れるというのは、英語が上手であること以前に、コミュニケーションに対して「体が開いてる」ということや、所属する大学や国に関係なく面白い研究に対して知的関心を持つということです。そして、そうしたコミュニケーションを取る上で、書いた論文や本の一節は次なるネットワーク作りのための名刺になります。
2024年、サバティカルでウィーンへ
在外研究を目的として私が滞在したウィーン大学には、東アジア研究所(Institut für Ostasienwissenschaften)という部門がありますが、ヨーロッパにおける、中国や日本、韓国、東南アジアなどに対する関心は私たちが思う以上に高いです。同研究所の知り合いの教授とお話しして、ヨーロッパの研究動向を知るために3ヶ月間現地に滞在しました。
この時はウィーンでの滞在でしたが、ケルン大学にもグローバルサウス研究センター(Das Global South Studies Center: GSSC)という研究所があり、アフリカや東南アジア等、グローバルサウスと言われる地域の事例を研究する研究者たちが、私のようにサバティカル(研究休暇)を取得して訪れて情報交換をする場ともなっています。
ドイツ語圏の社会学研究は理論が中心にはなるのですが、フィールドワークでも新しい研究に触れることができます。同じアジアの研究であっても、どのようなフレームワークでその社会を見るかという問題設定が日本とは違ったかたちで行われます。ですので、フィールドワークそのものというより、フィールドワークを行うための理論や方法、フレームワーク設定を学ぶための3ヵ月でした。

ウィーンでは、新しいテーマを発見できたことが一番面白かったです。たまたま参加したある研究会のセッションで、女性の夜の仕事、エンターテイナーの仕事をする人たちのエスノグラフィを発表した女性の社会学者がいました。ロンドンのナイトクラブでどんなことが行われてるのかという研究だったのですが、そこでたくさんの日本の女性が働いている実情を報告していました。日本人女性がロンドンのラウンジで接待をしているケースがあるということです。フィリピン人女性が日本や他の国で夜の仕事につくということについて私も話すことはありましたが、日本人女性が海外で夜の仕事に従事しているということは、調べれば分かるかもしれませんが、なかなか日本にいては気づきません。このようなテーマが研究対象になるのだというヒントが得られて、私にとっては刺激的な時間でした。
研究キャリアで最も苦しかった時期と、今、行き詰まりを感じている若手研究者に対するアドバイス
研究者というのは、若手に限らず行き詰まりを感じるものです。本来は私のように50前後の研究者の行き詰まりこそ問うべきなのかもしれませんが、若手研究者の行き詰まりということで言えば、やはり博士論文の執筆が一つの試練となるでしょう。そして博士論文を書いてからアカデミックなポストを得るまでが、誰もが経験する試練です。運も大きく左右すると思います。たまたま公募が出ていたとか、声が掛かったとか、運や偶然の部分も大きく、そこが苦しいところだと思います。
博士論文を書く時には自分の関心を文献や調査データとかに結びつけ、形を整えてロジックを組み立てるという作業を来る日も来る日も繰り返すのが辛いといえば辛いでしょう。しかしそれを繰り返すことで見える景色もあります。見晴らしの良い場所を走っても気持ちは良いですが、それ以上の新しい景色は見えません。見晴らしは悪くても、毎日少しずつ、例えば文献を一本読むといった実績を積み上げることを目標にするのがよいのではないかと思ってます。忙しくても何か一つ博論の完成に向けて今日も積み上げたという実感を持つことが大切でしょう。
研究に情熱を持ち続け、心身ともに健康に研究活動を続ける秘訣
2つあります。1つは、研究とは関係のない友達や時間を持つことです。私の場合、完全な趣味でボクシングジムに通っており、時間があれば1週間に1度ほど行き、リフレッシュします。24時間研究のことだけを考えて過ごすのでなく、研究以外の人間関係や時間、空間を持つようにしています。
2つ目は研究体制です。私がフィリピンに長期間滞在し調査できたのは、パートナーと子供たちと話をしながら調整できたという前提があります。しかし、親の介護や小さい子供の育児など、人生のステージで調整が難しいケースもあるはずで、そもそもひとりで子育てしているようなケースもあるわけです。実際、フィールドワークどころか、一晩の懇親会や歓迎会に行くことも難しい状況で研究されている方もたくさんいます。そうした時間調整の難しい状況にいる人でも研究を続けられるような研究体制を日本が作っていくことはとても重要だと思います。
研究者は家のことは放っておいて自分の研究に邁進する、というモデルがまだまだ政策的な発想では強いと思います。しかし持続性を考えれば、家から離れられない中でなんとか研究や教育に従事する人々が、それを続けていけるような時間や組織の配分に転換していくことも必要だと思います。そのあたりの問題提起はしていかなければならないでしょう。
日本の学術研究を発展させていく上で必要なこと
これは教授クラスの人々への提言になりますが、国際学会に参加しその中で研究仲間のネットワークを作るということです。そして各国の状況がメールなどで頻繁に入ってくるような状況にしていれば、学生と話す時でも、例えば東日本大震災の状況について阪神大震災だけを参照するのではなく、インドネシアのスマトラ島沖地震についてアメリカの研究者はこう書いている、チリのルポライターはこのような記事を出しているといったことも伝えられます。新型コロナのような感染症にしても、情報のフレーミングが限られているのは問題だと思います。
日本語だけの情報ではない発想を知るために国際的な研究仲間とつながって、彼らが何を書き、何に関心を持ち、グローバルな視点でどのように事態を見てるいるかを知るべきなのです。日本語の発想法から、少しでも複眼的な発想に移行するために、日常的にどう情報を取り入れていくかを注意することも必要だと思います。

制度面での提言として、若手研究者の海外派遣と育成があります。
私がドイツ語圏に行くようになったのは2014年です。学術振興会の国際交流事業部の日独先端科学シンポジウム(Japanese-German Frontiers of Science: JGFoS)というプログラムで、45歳以下の文系・理系の若手研究者を日本から30人、ドイツから30人集めて4日間ぐらい議論させる企画があり、それに選ばれました。そこからドイツ語圏の友達などもできました。
私自身がその恩恵を受けているのですが、若い研究者にもっとお金をつけ、外に行って研鑽を積む機会を持たせる必要があると思います。すでに働きだして、なかなか外国に行けなくなっている若手研究者を支援するという制度をさらに発展させていくことがますます重要になると思います。
脚注:
1 『ローカルボクサーと貧困世界』(世界思想社、2012 年/増補改訂版2024年)
2 『タイミングの社会学-ディテールを書くエスノグラフィー-』(青土社、2023 年)
3 “The personal is political.” 1960年代以降のアメリカのフェミニズムムーブメント、学生運動などにおけるスローガン。
